2012年02月28日
ウキを作る ~その後
2月28日(火)
先日作成したウキです。脚を黒く塗ると見た目が少し締まりました 。ウキトップ塗装用の黒いハケ付きラッカーを使いました。
。ウキトップ塗装用の黒いハケ付きラッカーを使いました。

この土日で、すでに実戦にも投入。あたりもばっちりわかりました。ボディー形状はもちろん大切だと思いますが、要はトップの浮力でエサを背負い、あたりを表現するわけなので、素人ウキにはトップの選択が非常に重要だなと思いました。これさえ、間違えなければ、とりあえずあたりを表現できるウキにはなるようです 。
。
さて、機能性は徐々に高めていくこととして、満足度をすぐに高めるには、見た目の改善ですね・・・ 。そこで、まず脚を竹で作成しました。
。そこで、まず脚を竹で作成しました。

左側です。右側はすでに1番目の写真の上端と下端が黒色の長い方のウキに仕上がってます。竹は編み棒0号を削って使いました。竹串でもいいのですが、焼き入れをしたり、曲げをとったりしないといけないので、すでにまっすぐにしてある編み棒は便利です 。
。
そして、やはり塗装です。ウレタン塗っておけば、機能的には問題ないのですが、やはりうるし(合成)を塗ってきれいなウキを作ってみたくなります。単色塗りはすでにやっていますが、研ぎだしなどの塗りはやったことがないので、まずは、不要な竹片で練習がてらに試し塗りをしてみました。

いろいろなホームページを見て、なんとなくこうするのかな?というやり方で実験してみました。とりあえず、それっぽく見えます 。
。
・・・ということで、この手法でいってみようと現在竹脚の2本を乾燥中です。

この次の工程が研ぎだし(水やすりで磨いて、中に重ねた色を出していきます)、それが終わると仕上げ塗りになります。
試し塗りの竹片より丁寧にやってしまったのが、吉と出るか凶と出るか微妙な感じ・・・ 。たぶん、大胆にやる方が、良い結果が生まれそうな気がしてます。
。たぶん、大胆にやる方が、良い結果が生まれそうな気がしてます。
まあ、こればかりは研いでみないとわからないので、後日のお楽しみということで・・・
先日作成したウキです。脚を黒く塗ると見た目が少し締まりました
 。ウキトップ塗装用の黒いハケ付きラッカーを使いました。
。ウキトップ塗装用の黒いハケ付きラッカーを使いました。
この土日で、すでに実戦にも投入。あたりもばっちりわかりました。ボディー形状はもちろん大切だと思いますが、要はトップの浮力でエサを背負い、あたりを表現するわけなので、素人ウキにはトップの選択が非常に重要だなと思いました。これさえ、間違えなければ、とりあえずあたりを表現できるウキにはなるようです
 。
。さて、機能性は徐々に高めていくこととして、満足度をすぐに高めるには、見た目の改善ですね・・・
 。そこで、まず脚を竹で作成しました。
。そこで、まず脚を竹で作成しました。
左側です。右側はすでに1番目の写真の上端と下端が黒色の長い方のウキに仕上がってます。竹は編み棒0号を削って使いました。竹串でもいいのですが、焼き入れをしたり、曲げをとったりしないといけないので、すでにまっすぐにしてある編み棒は便利です
 。
。そして、やはり塗装です。ウレタン塗っておけば、機能的には問題ないのですが、やはりうるし(合成)を塗ってきれいなウキを作ってみたくなります。単色塗りはすでにやっていますが、研ぎだしなどの塗りはやったことがないので、まずは、不要な竹片で練習がてらに試し塗りをしてみました。

いろいろなホームページを見て、なんとなくこうするのかな?というやり方で実験してみました。とりあえず、それっぽく見えます
 。
。・・・ということで、この手法でいってみようと現在竹脚の2本を乾燥中です。

この次の工程が研ぎだし(水やすりで磨いて、中に重ねた色を出していきます)、それが終わると仕上げ塗りになります。
試し塗りの竹片より丁寧にやってしまったのが、吉と出るか凶と出るか微妙な感じ・・・
 。たぶん、大胆にやる方が、良い結果が生まれそうな気がしてます。
。たぶん、大胆にやる方が、良い結果が生まれそうな気がしてます。まあ、こればかりは研いでみないとわからないので、後日のお楽しみということで・・・

2012年02月23日
1日でウキを作る Part3
2月23日(木)
【Part3:塗装】
塗装は、ボディー部だけにします。性能にはほとんど影響ないでしょうから、脚はソリッドむき出しです。パイプトップも今回はすでに着色された既製品を使用することにしました。
まず、上下の絞り部分の溝を隠すために、厚化粧することに・・・ 。合成うるしを塗ればできるのですが、乾燥時間が丸一日かかります。しかも何度か重ね塗りをしなければなりませんので数日かかります。1日でウキを作るのが目標なので、まず家にあったアクリル絵の具を使ってみました。
。合成うるしを塗ればできるのですが、乾燥時間が丸一日かかります。しかも何度か重ね塗りをしなければなりませんので数日かかります。1日でウキを作るのが目標なので、まず家にあったアクリル絵の具を使ってみました。
マスキングをして塗りましたが、マスキングテープとの境目に段差ができてしまうので、乾いてすぐに剥がしました 。でも、あら不思議・・・溝には絵の具がしっかりと入り、パテ埋め状態になってました
。でも、あら不思議・・・溝には絵の具がしっかりと入り、パテ埋め状態になってました (まあ着色する場合には、普通に木材用パテで埋めればいいだけのことなんですけど・・・)。
(まあ着色する場合には、普通に木材用パテで埋めればいいだけのことなんですけど・・・)。

・・・で、もっとも邪道かつ簡単な方法のマジックで塗ることにしました。この前ハンズで購入したCOPICを使いました。自作竿に名入れとかする目的で、衝動買いしたのですが(高いです。1本450円もします・・・ )、水性顔料インクで、乾くと耐水性ということで、製図やマンガを描く人とかが使っているそうです。油性ペンだと塗装と反応して、インク流れが起こるようなので、ご注意ください。ついでにこの段階でウキに名入れをしました。(【後日談】:名入れや水性塗料での着色は、下地用のウレタンを塗って乾燥させ、ヤスリで軽く磨いて、平らにした後がたぶん正解です。)
)、水性顔料インクで、乾くと耐水性ということで、製図やマンガを描く人とかが使っているそうです。油性ペンだと塗装と反応して、インク流れが起こるようなので、ご注意ください。ついでにこの段階でウキに名入れをしました。(【後日談】:名入れや水性塗料での着色は、下地用のウレタンを塗って乾燥させ、ヤスリで軽く磨いて、平らにした後がたぶん正解です。)

水性マジックのため、すぐに乾きますので、次に一番簡単な1液性ウレタン塗料のドブ付けをしました。後ろに写った2本は東京でボディーを作った分です。

早く乾かすために、風呂場の暖房をつけてやりました。2度塗りの予定でしたので、次が塗りたくて我慢してましたが、4時間経ったところで我慢も限界になったので、少し早いかなと思いつつ2度目を・・・。今度はもっと早く乾かしてやろうと暖房用のオイルヒーターの上部に吊るして強制的に乾かしました 。・・・が、同様に4時間待ってウキを見ると表面に泡やブツブツが・・・
。・・・が、同様に4時間待ってウキを見ると表面に泡やブツブツが・・・ 。1度目のが十分に乾いていなかったため、しわが出たのか、熱で気泡でも出てしまったのでしょうか・・・
。1度目のが十分に乾いていなかったため、しわが出たのか、熱で気泡でも出てしまったのでしょうか・・・ 。仕方ないので、表面の泡やぶつぶつを1000番ヤスリで軽く水研ぎし、3度目塗りました。ただ、ちょうど夜でしたので、そのまま就寝しました
。仕方ないので、表面の泡やぶつぶつを1000番ヤスリで軽く水研ぎし、3度目塗りました。ただ、ちょうど夜でしたので、そのまま就寝しました 。
。
そして翌朝になり、しっかりと乾燥しているのを確認。自動車用のコンパウンドで磨き、塗装は完了。次は実際に水に浮かせて最終調整です。そのままだとトップが長すぎてバランスが悪いので、トップを少し切るとともに、もう少しオモリを背負えるように脚も切って、2Bの錘で(フカセマンには、ガンダマがイメージしやすい )バランスするように調整しました。針とサルカンを付けたエサ落ち目盛は、もう1~2目盛上になるでしょうから、ぴったりです。なお、トップを長くし過ぎると、表面張力が勝って、立たないウキになりますので、ご注意ください(石鹸でウキを洗うと大丈夫になるケースもあります)。
)バランスするように調整しました。針とサルカンを付けたエサ落ち目盛は、もう1~2目盛上になるでしょうから、ぴったりです。なお、トップを長くし過ぎると、表面張力が勝って、立たないウキになりますので、ご注意ください(石鹸でウキを洗うと大丈夫になるケースもあります)。

最後にトップを瞬間接着剤でとめて完成です
 。強制乾燥の塗装事故があったので、前日中に完成しませんでしたが、前日は昼から始めたので、24時間以内で完成しました
。強制乾燥の塗装事故があったので、前日中に完成しませんでしたが、前日は昼から始めたので、24時間以内で完成しました 。ウレタン2度塗りなら十分その日の内に完成できたと思います。
。ウレタン2度塗りなら十分その日の内に完成できたと思います。
東京でボディーを作った分は、先週家に戻ってから、エポキシボンドを下塗りと防水のための塗料代わりに、ウレタン薄め液で薄めて塗りました(邪道です )。乾燥させるのに普通10分のものが、丸1日かかりました・・・
)。乾燥させるのに普通10分のものが、丸1日かかりました・・・ )。そして、その上から合成うるしの透と透明を混ぜて、3度塗りしました(3日間)。木工用ボンドを乾かすのにも2晩かかってましたから(最初の接着と修正の接着)、結局約1週間かかったことになります
)。そして、その上から合成うるしの透と透明を混ぜて、3度塗りしました(3日間)。木工用ボンドを乾かすのにも2晩かかってましたから(最初の接着と修正の接着)、結局約1週間かかったことになります 。
。
今回のように瞬間接着剤を使用して製作した場合、失敗すると調整不可で後戻りできませんが、すぐにやり直せるので、作り方に慣れるまではこの方法でやって、上手になったら精度や塗りも意識して、じっくり取り組むのが良いのではと思いました 。
。
以上、「1日でウキを作る」でした。お粗末さまでした 。
。
【Part3:塗装】
塗装は、ボディー部だけにします。性能にはほとんど影響ないでしょうから、脚はソリッドむき出しです。パイプトップも今回はすでに着色された既製品を使用することにしました。
まず、上下の絞り部分の溝を隠すために、厚化粧することに・・・
 。合成うるしを塗ればできるのですが、乾燥時間が丸一日かかります。しかも何度か重ね塗りをしなければなりませんので数日かかります。1日でウキを作るのが目標なので、まず家にあったアクリル絵の具を使ってみました。
。合成うるしを塗ればできるのですが、乾燥時間が丸一日かかります。しかも何度か重ね塗りをしなければなりませんので数日かかります。1日でウキを作るのが目標なので、まず家にあったアクリル絵の具を使ってみました。マスキングをして塗りましたが、マスキングテープとの境目に段差ができてしまうので、乾いてすぐに剥がしました
 。でも、あら不思議・・・溝には絵の具がしっかりと入り、パテ埋め状態になってました
。でも、あら不思議・・・溝には絵の具がしっかりと入り、パテ埋め状態になってました (まあ着色する場合には、普通に木材用パテで埋めればいいだけのことなんですけど・・・)。
(まあ着色する場合には、普通に木材用パテで埋めればいいだけのことなんですけど・・・)。
・・・で、もっとも邪道かつ簡単な方法のマジックで塗ることにしました。この前ハンズで購入したCOPICを使いました。自作竿に名入れとかする目的で、衝動買いしたのですが(高いです。1本450円もします・・・
 )、水性顔料インクで、乾くと耐水性ということで、製図やマンガを描く人とかが使っているそうです。油性ペンだと塗装と反応して、インク流れが起こるようなので、ご注意ください。ついでにこの段階でウキに名入れをしました。(【後日談】:名入れや水性塗料での着色は、下地用のウレタンを塗って乾燥させ、ヤスリで軽く磨いて、平らにした後がたぶん正解です。)
)、水性顔料インクで、乾くと耐水性ということで、製図やマンガを描く人とかが使っているそうです。油性ペンだと塗装と反応して、インク流れが起こるようなので、ご注意ください。ついでにこの段階でウキに名入れをしました。(【後日談】:名入れや水性塗料での着色は、下地用のウレタンを塗って乾燥させ、ヤスリで軽く磨いて、平らにした後がたぶん正解です。)
水性マジックのため、すぐに乾きますので、次に一番簡単な1液性ウレタン塗料のドブ付けをしました。後ろに写った2本は東京でボディーを作った分です。

早く乾かすために、風呂場の暖房をつけてやりました。2度塗りの予定でしたので、次が塗りたくて我慢してましたが、4時間経ったところで我慢も限界になったので、少し早いかなと思いつつ2度目を・・・。今度はもっと早く乾かしてやろうと暖房用のオイルヒーターの上部に吊るして強制的に乾かしました
 。・・・が、同様に4時間待ってウキを見ると表面に泡やブツブツが・・・
。・・・が、同様に4時間待ってウキを見ると表面に泡やブツブツが・・・ 。1度目のが十分に乾いていなかったため、しわが出たのか、熱で気泡でも出てしまったのでしょうか・・・
。1度目のが十分に乾いていなかったため、しわが出たのか、熱で気泡でも出てしまったのでしょうか・・・ 。仕方ないので、表面の泡やぶつぶつを1000番ヤスリで軽く水研ぎし、3度目塗りました。ただ、ちょうど夜でしたので、そのまま就寝しました
。仕方ないので、表面の泡やぶつぶつを1000番ヤスリで軽く水研ぎし、3度目塗りました。ただ、ちょうど夜でしたので、そのまま就寝しました 。
。そして翌朝になり、しっかりと乾燥しているのを確認。自動車用のコンパウンドで磨き、塗装は完了。次は実際に水に浮かせて最終調整です。そのままだとトップが長すぎてバランスが悪いので、トップを少し切るとともに、もう少しオモリを背負えるように脚も切って、2Bの錘で(フカセマンには、ガンダマがイメージしやすい
 )バランスするように調整しました。針とサルカンを付けたエサ落ち目盛は、もう1~2目盛上になるでしょうから、ぴったりです。なお、トップを長くし過ぎると、表面張力が勝って、立たないウキになりますので、ご注意ください(石鹸でウキを洗うと大丈夫になるケースもあります)。
)バランスするように調整しました。針とサルカンを付けたエサ落ち目盛は、もう1~2目盛上になるでしょうから、ぴったりです。なお、トップを長くし過ぎると、表面張力が勝って、立たないウキになりますので、ご注意ください(石鹸でウキを洗うと大丈夫になるケースもあります)。
最後にトップを瞬間接着剤でとめて完成です

 。強制乾燥の塗装事故があったので、前日中に完成しませんでしたが、前日は昼から始めたので、24時間以内で完成しました
。強制乾燥の塗装事故があったので、前日中に完成しませんでしたが、前日は昼から始めたので、24時間以内で完成しました 。ウレタン2度塗りなら十分その日の内に完成できたと思います。
。ウレタン2度塗りなら十分その日の内に完成できたと思います。東京でボディーを作った分は、先週家に戻ってから、エポキシボンドを下塗りと防水のための塗料代わりに、ウレタン薄め液で薄めて塗りました(邪道です
 )。乾燥させるのに普通10分のものが、丸1日かかりました・・・
)。乾燥させるのに普通10分のものが、丸1日かかりました・・・ )。そして、その上から合成うるしの透と透明を混ぜて、3度塗りしました(3日間)。木工用ボンドを乾かすのにも2晩かかってましたから(最初の接着と修正の接着)、結局約1週間かかったことになります
)。そして、その上から合成うるしの透と透明を混ぜて、3度塗りしました(3日間)。木工用ボンドを乾かすのにも2晩かかってましたから(最初の接着と修正の接着)、結局約1週間かかったことになります 。
。今回のように瞬間接着剤を使用して製作した場合、失敗すると調整不可で後戻りできませんが、すぐにやり直せるので、作り方に慣れるまではこの方法でやって、上手になったら精度や塗りも意識して、じっくり取り組むのが良いのではと思いました
 。
。以上、「1日でウキを作る」でした。お粗末さまでした
 。
。 2012年02月22日
1日でウキを作る Part2
2月22日(水)
【Part2:ボディー成型】
では、塗装する前までのボディーを成型するところです。まずは、切削が完了したカヤの中心部分にグラスソリッドをゆっくりとまっすぐになるように慎重に差し込んでみます。

今回はウキのボディーが6cmと短いので、通し差しにすることにしましたが、脚には竹やカーボンなど違う素材や違う径のソリッドを使用するケースも多く、おまけにソリッドの通し差しだと少し重くなるので、脚とトップのソリッドは別のものを使うことの方が一般的だと思います。

写真のようにカッティングボードの線などを見ながらやると、わりとまっすぐ入れやすいと思います。なお、写真のカッティングボードはアメリカ在住時に購入したものなので、数字はインチ表示で、cmではありませんのでご注意ください。
次に指し込んだソリッドを一旦抜き、ゼリータイプの瞬間接着剤をボディーの中心部の穴を目がけて垂らします。そしてソリッドを回しながら一気に指し込みます。回しながらすると接着剤が中に入っていきます。ゆっくりやりすぎると途中で瞬間接着剤が固まってしまい、どうしようもなくなります 。わたしは間一髪でした
。わたしは間一髪でした 。
。
そして今度は開いた部分に液体の瞬間接着剤を塗ってから、すばやくタコ糸をグルグル巻きにしました。マスキングテープは巻いたままでOK。糸が滑らないので簡単に巻けます。トップとボトムと順にやります。おそらく状態が見えるからだと思いますが、一般的には細い糸を隙間をあけて巻くようです。太いタコ糸だと状態は見ませんが、瞬間接着剤を使用しているのでいずれにせよ修正は効かないため、全体的に力が入りやすい太いタコ糸を使用しました。

5分もすれば乾いていますので、慎重に糸をほどきます。糸も瞬間接着剤で少し固まっていましたが、それほど苦労せずに取れました。

次にマスキングテープがあるので、それもはずしました。カヤの表面はそれほど瞬間接着剤がついていませんでしたが、少々ガビガビにはなっていました 。
。

そして、全体的に紙やすり400番程度で磨きました。ガビガビは簡単に取れました。・・・が、あわせの部分に隙間がありました。木工用ボンドでつけていると、この程度は瞬間接着剤をつけて再度糸で縛ると簡単に修正できるのですが、最初から瞬間接着剤なので、修正不可です。塗りのところでごまかすことにしました。試しにトップも付けてみました。良い感じです
 。
。

~ 【Part3:塗装】に続く ~
【Part2:ボディー成型】
では、塗装する前までのボディーを成型するところです。まずは、切削が完了したカヤの中心部分にグラスソリッドをゆっくりとまっすぐになるように慎重に差し込んでみます。

今回はウキのボディーが6cmと短いので、通し差しにすることにしましたが、脚には竹やカーボンなど違う素材や違う径のソリッドを使用するケースも多く、おまけにソリッドの通し差しだと少し重くなるので、脚とトップのソリッドは別のものを使うことの方が一般的だと思います。

写真のようにカッティングボードの線などを見ながらやると、わりとまっすぐ入れやすいと思います。なお、写真のカッティングボードはアメリカ在住時に購入したものなので、数字はインチ表示で、cmではありませんのでご注意ください。
次に指し込んだソリッドを一旦抜き、ゼリータイプの瞬間接着剤をボディーの中心部の穴を目がけて垂らします。そしてソリッドを回しながら一気に指し込みます。回しながらすると接着剤が中に入っていきます。ゆっくりやりすぎると途中で瞬間接着剤が固まってしまい、どうしようもなくなります
 。わたしは間一髪でした
。わたしは間一髪でした 。
。そして今度は開いた部分に液体の瞬間接着剤を塗ってから、すばやくタコ糸をグルグル巻きにしました。マスキングテープは巻いたままでOK。糸が滑らないので簡単に巻けます。トップとボトムと順にやります。おそらく状態が見えるからだと思いますが、一般的には細い糸を隙間をあけて巻くようです。太いタコ糸だと状態は見ませんが、瞬間接着剤を使用しているのでいずれにせよ修正は効かないため、全体的に力が入りやすい太いタコ糸を使用しました。

5分もすれば乾いていますので、慎重に糸をほどきます。糸も瞬間接着剤で少し固まっていましたが、それほど苦労せずに取れました。

次にマスキングテープがあるので、それもはずしました。カヤの表面はそれほど瞬間接着剤がついていませんでしたが、少々ガビガビにはなっていました
 。
。
そして、全体的に紙やすり400番程度で磨きました。ガビガビは簡単に取れました。・・・が、あわせの部分に隙間がありました。木工用ボンドでつけていると、この程度は瞬間接着剤をつけて再度糸で縛ると簡単に修正できるのですが、最初から瞬間接着剤なので、修正不可です。塗りのところでごまかすことにしました。試しにトップも付けてみました。良い感じです

 。
。
~ 【Part3:塗装】に続く ~
2012年02月21日
1日でウキを作る Part1
2月21日(火)
ヘラ用に竿掛けや玉網、竿まで作ったのだから、やはりウキも作らんとあかんな~と・・・ 。
。
先週ちょっと記事にした通り、東京へ仕事に行っている間にホテルでウキのボディー作りをやってみましたが、結構時間がかかりました。トップと脚の絞り部分の切りだしは刃が一気に入って失敗したり、紙ヤスリで削っているとカヤ素材が割れたりします。その上、木工用ボンドは乾燥に時間がかかるので、修正はしやすいのですが、すぐに次の作業に移れません。釣りをする人は気が短いとよく言いますが、ご多分にもれず、わたしも接着剤や塗装の乾燥待ちが大嫌いです 。
。
もちろん丁寧に作業し、時間も余裕を持って、作る方が良い物ができるのはわかっていますが、もっと簡単に、しかも早く仕上げる方法はないものかと考えながら、1日でウキを作るを目指してみることにしました 。
。
なお、カヤウキ作りの基本は、東邦産業のHPにあるヘラ浮子の作り方を主に参照しました。
まず今回の材料および製作道具です。
・ 5~6mm径のカヤ
・ グラスソリッドの1mm(脚およびパイプトップ固定用ソリッド)
・ 既成のテーパー付き極細パイプトップ(長さ12mm、元外径1.2mm、元内径約0.8mm)
・ 100円ショップの瞬間接着剤(液体とゼリーの2種)
・ OLFAの超極薄0.2mmのカッター(片刃カミソリを見つけられなかったので)
・ マスキング用テープ(医療用の包帯止めるようなやつ)
・ タコ糸
・ 紙ヤスリ(240番、400番、600番、1000番)
・ 1液性ウレタン
・ マジックとアクリル絵の具、定規、はさみ、その他
今回の完成品です 。
。

なお、以下に記載する製作方法はウキ作り初心者によるお試し的なものなので、次回はぜんぜん違う方法で作っているかもしれません。あしからず・・・。経験者の皆様、もっと簡単に作る方法をご存知でしたら、ぜひ教えてください。よろしく~ 。では、ウキ作りのスタートです
。では、ウキ作りのスタートです 。
。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【Part1:カヤ切削】
まずカヤを今回は6cmにカット。前回東京では10cmでやりました。転がしながらカッターで切り、切り口はヤスリで整えました。前回絞り部分を切りこむのに苦労したので、トップと脚ともに絞り予定部分(+α)にテープを貼り、洗面所からメイク用ハサミをこっそり取り出し 、それで切って仕上げることを考えましたが、実験するとやはりカヤが割れてしまいましたので、その方法は却下。
、それで切って仕上げることを考えましたが、実験するとやはりカヤが割れてしまいましたので、その方法は却下。
そこで、テープは鉛筆で線を引けるようにマスキング用テープに変え、普通にカッターで切ることにしました(カッターは極薄刃でないと素材が割れます)。今回は、トップの絞りを8mm、脚の絞りを30mmにしました。

一般的には、テープは貼らずに青線部分のように4分割してから、赤線のところまで、少しずつカッターや紙やすりで整えていくようですが、マスキングテープにきっちりと図面を描いているので、いきなり赤線のところを斜めに刃を入れて切っていきました。少しずつ慎重に削らなくてよい上に、テープで刃が滑らず簡単に切れたので、作業時間は少なく済みました 。おまけに面倒なので、定規などは使わずフリーハンドで線を描いてます
。おまけに面倒なので、定規などは使わずフリーハンドで線を描いてます 。。(【後日談】:定規あるいはプラスティックの板等を使用して、線をきっちり描くと、隙間も少なく、仕上がりがかなりきれいになりますので、こちらがお勧めです。)
。。(【後日談】:定規あるいはプラスティックの板等を使用して、線をきっちり描くと、隙間も少なく、仕上がりがかなりきれいになりますので、こちらがお勧めです。)
これが切った直後の写真です。かなり適当なことがお分かりいただけるでしょう・・・(笑)。

次に溝部分に紙やすりを差し込んで側面にもあてながら前後に軽く往復して削っていきました。

まったく力を入れる必要はなく、無理にワタを取ろうとしなくても簡単に削れました。そして、紙やすりを反対向きにして、反対面も・・・。そして90度回して同様に。深さが予定の絞り幅の線に達するところまで削ります。
削り終えるとこんな感じになりました 。
。

意外とうまくいきました 。
。
脚側の絞りも同様にカッターで切って、紙やすりを差し込んで削って、カヤ切削の工程はあっという間に終了しました 。
。
~ 【Part2:ボディー成型】に続く ~
ヘラ用に竿掛けや玉網、竿まで作ったのだから、やはりウキも作らんとあかんな~と・・・
 。
。先週ちょっと記事にした通り、東京へ仕事に行っている間にホテルでウキのボディー作りをやってみましたが、結構時間がかかりました。トップと脚の絞り部分の切りだしは刃が一気に入って失敗したり、紙ヤスリで削っているとカヤ素材が割れたりします。その上、木工用ボンドは乾燥に時間がかかるので、修正はしやすいのですが、すぐに次の作業に移れません。釣りをする人は気が短いとよく言いますが、ご多分にもれず、わたしも接着剤や塗装の乾燥待ちが大嫌いです
 。
。もちろん丁寧に作業し、時間も余裕を持って、作る方が良い物ができるのはわかっていますが、もっと簡単に、しかも早く仕上げる方法はないものかと考えながら、1日でウキを作るを目指してみることにしました
 。
。なお、カヤウキ作りの基本は、東邦産業のHPにあるヘラ浮子の作り方を主に参照しました。
まず今回の材料および製作道具です。
・ 5~6mm径のカヤ
・ グラスソリッドの1mm(脚およびパイプトップ固定用ソリッド)
・ 既成のテーパー付き極細パイプトップ(長さ12mm、元外径1.2mm、元内径約0.8mm)
・ 100円ショップの瞬間接着剤(液体とゼリーの2種)
・ OLFAの超極薄0.2mmのカッター(片刃カミソリを見つけられなかったので)
・ マスキング用テープ(医療用の包帯止めるようなやつ)
・ タコ糸
・ 紙ヤスリ(240番、400番、600番、1000番)
・ 1液性ウレタン
・ マジックとアクリル絵の具、定規、はさみ、その他
今回の完成品です
 。
。
なお、以下に記載する製作方法はウキ作り初心者によるお試し的なものなので、次回はぜんぜん違う方法で作っているかもしれません。あしからず・・・。経験者の皆様、もっと簡単に作る方法をご存知でしたら、ぜひ教えてください。よろしく~
 。では、ウキ作りのスタートです
。では、ウキ作りのスタートです 。
。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【Part1:カヤ切削】
まずカヤを今回は6cmにカット。前回東京では10cmでやりました。転がしながらカッターで切り、切り口はヤスリで整えました。前回絞り部分を切りこむのに苦労したので、トップと脚ともに絞り予定部分(+α)にテープを貼り、洗面所からメイク用ハサミをこっそり取り出し
 、それで切って仕上げることを考えましたが、実験するとやはりカヤが割れてしまいましたので、その方法は却下。
、それで切って仕上げることを考えましたが、実験するとやはりカヤが割れてしまいましたので、その方法は却下。そこで、テープは鉛筆で線を引けるようにマスキング用テープに変え、普通にカッターで切ることにしました(カッターは極薄刃でないと素材が割れます)。今回は、トップの絞りを8mm、脚の絞りを30mmにしました。

一般的には、テープは貼らずに青線部分のように4分割してから、赤線のところまで、少しずつカッターや紙やすりで整えていくようですが、マスキングテープにきっちりと図面を描いているので、いきなり赤線のところを斜めに刃を入れて切っていきました。少しずつ慎重に削らなくてよい上に、テープで刃が滑らず簡単に切れたので、作業時間は少なく済みました
 。おまけに面倒なので、定規などは使わずフリーハンドで線を描いてます
。おまけに面倒なので、定規などは使わずフリーハンドで線を描いてます 。。(【後日談】:定規あるいはプラスティックの板等を使用して、線をきっちり描くと、隙間も少なく、仕上がりがかなりきれいになりますので、こちらがお勧めです。)
。。(【後日談】:定規あるいはプラスティックの板等を使用して、線をきっちり描くと、隙間も少なく、仕上がりがかなりきれいになりますので、こちらがお勧めです。)これが切った直後の写真です。かなり適当なことがお分かりいただけるでしょう・・・(笑)。

次に溝部分に紙やすりを差し込んで側面にもあてながら前後に軽く往復して削っていきました。

まったく力を入れる必要はなく、無理にワタを取ろうとしなくても簡単に削れました。そして、紙やすりを反対向きにして、反対面も・・・。そして90度回して同様に。深さが予定の絞り幅の線に達するところまで削ります。
削り終えるとこんな感じになりました
 。
。
意外とうまくいきました
 。
。脚側の絞りも同様にカッターで切って、紙やすりを差し込んで削って、カヤ切削の工程はあっという間に終了しました
 。
。~ 【Part2:ボディー成型】に続く ~
2012年02月21日
竿2号緊急入院
2月19日(日)
昨日、釣り場で曲がってしまった自作竿2号。元竿部分が曲がったと思っていたのですが、家に戻り調べてみると、穂持ち(2番目)の元竿へ差し込む凸の部分にひびが入っていました 。
。
固めて補修してもまた折れそうなので、原因を調べるためにひびの入っているところを思い切って切断してみました 。
。

原因がいくつか判明しました 。
。
まず明らかなのが補強芯。ホームセンターの園芸竹ということもあり、テーパーのきちんとした竹はなかなかありません。穂持ちと元竿の長さを合わせることを優先したので、込み(凸)に加工した部分は長い節間のペニャンペニャン部分でした。竹の表皮を削ったこともあり、ますます弱くなっているので、竹串を芯材に入れて補強していたのですが、芯材を入れるために穴をあけるドリルの長さが足らず、芯材を十分に深くまで入れていませんでした。そのせいで、ちょうど継ぎ目の一番力のかかるところに芯材の先端が来てしまい、それより元側は強く、先側は弱くなりますので、強度に差があり、そこで折れてしまったようです 。
。
次に穂持ちに使った竹は、節と節の中間が膨らんでおり、そのまま作ると込み(凸)が太くなりすぎるため、表皮を削って太さを調整していました。その表皮を削り弱くなった部分に元竿の継ぎ口(凹部先端)があたるようになっていたので、気にしてはいたのですが・・・。まさにそこでした 。
。
そして、込み口の作りの甘さ。差し込んで竿を振ると、少しギシギシいってました 。込み口(凹)と込み(凸)のテーパーがきっちりあっていないのだと思います。それゆえ力が分散されず、特定の場所に力が掛かっていたのだと思います。
。込み口(凹)と込み(凸)のテーパーがきっちりあっていないのだと思います。それゆえ力が分散されず、特定の場所に力が掛かっていたのだと思います。
穂先はとてもいいカーブを描いていました。良い感じだったのですが、もしかすると穂先が穂持ちに比べて強すぎたかもしれません。
・・・ということで、竿は少し短くはなりましたが、補強のための竹串を今度は深く入れなおし、表皮を削っていない場所に継ぎ口(凹部先端)があたるように込み(凸部)調整をして、とりあえずの修理としました 。
。

ただ、また折れるかもしれませんので、再度材料を吟味して、3号竿に向けて生地組みからボチボチ開始していこうと思います 。プロの竿は、込み部分の(凸)先端の方に竹の節をおくように生地組みしているケースが多いようです。
。プロの竿は、込み部分の(凸)先端の方に竹の節をおくように生地組みしているケースが多いようです。
昨日、釣り場で曲がってしまった自作竿2号。元竿部分が曲がったと思っていたのですが、家に戻り調べてみると、穂持ち(2番目)の元竿へ差し込む凸の部分にひびが入っていました
 。
。固めて補修してもまた折れそうなので、原因を調べるためにひびの入っているところを思い切って切断してみました
 。
。
原因がいくつか判明しました
 。
。まず明らかなのが補強芯。ホームセンターの園芸竹ということもあり、テーパーのきちんとした竹はなかなかありません。穂持ちと元竿の長さを合わせることを優先したので、込み(凸)に加工した部分は長い節間のペニャンペニャン部分でした。竹の表皮を削ったこともあり、ますます弱くなっているので、竹串を芯材に入れて補強していたのですが、芯材を入れるために穴をあけるドリルの長さが足らず、芯材を十分に深くまで入れていませんでした。そのせいで、ちょうど継ぎ目の一番力のかかるところに芯材の先端が来てしまい、それより元側は強く、先側は弱くなりますので、強度に差があり、そこで折れてしまったようです
 。
。次に穂持ちに使った竹は、節と節の中間が膨らんでおり、そのまま作ると込み(凸)が太くなりすぎるため、表皮を削って太さを調整していました。その表皮を削り弱くなった部分に元竿の継ぎ口(凹部先端)があたるようになっていたので、気にしてはいたのですが・・・。まさにそこでした
 。
。そして、込み口の作りの甘さ。差し込んで竿を振ると、少しギシギシいってました
 。込み口(凹)と込み(凸)のテーパーがきっちりあっていないのだと思います。それゆえ力が分散されず、特定の場所に力が掛かっていたのだと思います。
。込み口(凹)と込み(凸)のテーパーがきっちりあっていないのだと思います。それゆえ力が分散されず、特定の場所に力が掛かっていたのだと思います。穂先はとてもいいカーブを描いていました。良い感じだったのですが、もしかすると穂先が穂持ちに比べて強すぎたかもしれません。
・・・ということで、竿は少し短くはなりましたが、補強のための竹串を今度は深く入れなおし、表皮を削っていない場所に継ぎ口(凹部先端)があたるように込み(凸部)調整をして、とりあえずの修理としました
 。
。
ただ、また折れるかもしれませんので、再度材料を吟味して、3号竿に向けて生地組みからボチボチ開始していこうと思います
 。プロの竿は、込み部分の(凸)先端の方に竹の節をおくように生地組みしているケースが多いようです。
。プロの竿は、込み部分の(凸)先端の方に竹の節をおくように生地組みしているケースが多いようです。2012年02月08日
竿2号改造
2月8日(水)
先日、へら用の2号竿を製作し、実釣に使ってみようと思っていたのですが、その数日後に知り合いから本物の竹のへら竿をいただいてしまい、そのあまりもの違いに愕然として 、自作の2号竿を使えなくなってしまいました
、自作の2号竿を使えなくなってしまいました 。
。
それ以来、本物を参考に穂持ち(穂先の次)を違う竹に変更して組み直し、穂先はカーボンから竹に、塗装もやり直し・・・と作業を進めて2号竿を改造しました。まだ仕上げの拭き塗りをしていませんが、ほぼ完成。8.3尺です。今度こそ、実釣してみたいと思います 。
。
塗装は前回は継ぎ口はエポキシで先に固め、仕上げに全体にウレタンを塗っていたのですが、今回は高級うるしや特製うるしなど、いわゆる合成うるしの類で塗装してみることにしました。継ぎ口は塗装をはがし、糸巻きからやり直しました。また竿の胴部分もウレタン塗装をヤスリで少し削ってからうるしを塗りました。これは本漆ではないので、かぶれないし、色も和竿らしい色がでるのでいい感じです。ただ、エポキシやウレタンに比べると乾燥時間がかかる上に、何度も塗り重ねないといけないのです。面倒で、ついつい分厚く塗ってしまい、こんなことになってしまいました 。
。

まだら模様です・・・ 。本当は「透明」という色を何度も塗ると少し濃い色になっていい感じになるはずだったのですが、一度目に塗ったときにあまりに色が薄かったので、面倒になり「透(すき)」という濃い目の色をしかも分厚く塗ってしまったのです
。本当は「透明」という色を何度も塗ると少し濃い色になっていい感じになるはずだったのですが、一度目に塗ったときにあまりに色が薄かったので、面倒になり「透(すき)」という濃い目の色をしかも分厚く塗ってしまったのです 。乾燥後、あまりにかっこ悪かったので、削ったのですが、もともと凹んでいる部分は、削っても塗装が取れず、これ以上削ると籐自体が削れてしまいそうだったので、あきらめてまだら模様を選択することになったわけです。できあがれば、まあこれはこれでええっか~という感じです。では拡大写真
。乾燥後、あまりにかっこ悪かったので、削ったのですが、もともと凹んでいる部分は、削っても塗装が取れず、これ以上削ると籐自体が削れてしまいそうだったので、あきらめてまだら模様を選択することになったわけです。できあがれば、まあこれはこれでええっか~という感じです。では拡大写真 。
。

中央の黒い部分は、前回エギのアワビシートをあしらってみたのですが、わが息子に「かっこ悪い」と不評でしたので、それを取り除きました。そして、かわりに継ぎ口の糸巻き部とともに金粉を降りかけてみましたが、ちょっと全体にかけ過ぎてどこかのケバいおねえちゃんのネイルのようになってしまいました 。まあ、これも実験ということでOKでしょう。全体的にまだ少しデコボコはありますが、まあドシロートの1作目はこんなもんでしょう
。まあ、これも実験ということでOKでしょう。全体的にまだ少しデコボコはありますが、まあドシロートの1作目はこんなもんでしょう 。
。

こちらは継ぎ口部分です。やはり金粉をいっぱい付けたので、ピカピカ のネイル状態です。拡大写真はこちら
のネイル状態です。拡大写真はこちら 。
。

糸巻きは今回かなり細い糸を使いましたので、盛り上がりも少なくいい感じにできました。ただ、細い糸は巻くのも時間がかかるので面倒です。途中でロッドモーターで竿を回しながら巻く方法を試すと、結構簡単に巻けるようになりましたので、次回からはその方法でいきます 。
。
最後に穂先です。「竹で穂先を作ってやる」、これが今回の改造の大きなテーマでした。ホームセンターで真竹?の平たい割竹を一本購入(確か150円程度)。それを削って作りました 。
。

まずは竹を細く切り、そしてカンナで四角柱を作り、さらに強い表皮部分は残すようにカンナを入れてテーパーをつけた四角錐にします。そして角を取って八角錐に、そこからはヤスリを使い円錐形に、そしてドリルに尻部を挟み、回しながら紙やすりで仕上げていきます。途中火入れを何度もしながらまっすぐにしていきます。まだほんの少し曲がっていますが、OKということにしておきましょう。何とかできましたが、穂先作りはとても大変な作業でした(でも楽しい・・・ )。
)。
竿作り全体を通じての感想は、とにかくとても面倒で根気のいる作業の連続でした。ただ仕上がった時には、達成感と満足感が満タンでした。問題はここからです・・・継ぎ口の部分は調子に乗って削りすぎて、かなり薄いんです。なので、実釣で「ポキッ」っといかないように願うばかりです 。
。
先日、へら用の2号竿を製作し、実釣に使ってみようと思っていたのですが、その数日後に知り合いから本物の竹のへら竿をいただいてしまい、そのあまりもの違いに愕然として
 、自作の2号竿を使えなくなってしまいました
、自作の2号竿を使えなくなってしまいました 。
。それ以来、本物を参考に穂持ち(穂先の次)を違う竹に変更して組み直し、穂先はカーボンから竹に、塗装もやり直し・・・と作業を進めて2号竿を改造しました。まだ仕上げの拭き塗りをしていませんが、ほぼ完成。8.3尺です。今度こそ、実釣してみたいと思います
 。
。塗装は前回は継ぎ口はエポキシで先に固め、仕上げに全体にウレタンを塗っていたのですが、今回は高級うるしや特製うるしなど、いわゆる合成うるしの類で塗装してみることにしました。継ぎ口は塗装をはがし、糸巻きからやり直しました。また竿の胴部分もウレタン塗装をヤスリで少し削ってからうるしを塗りました。これは本漆ではないので、かぶれないし、色も和竿らしい色がでるのでいい感じです。ただ、エポキシやウレタンに比べると乾燥時間がかかる上に、何度も塗り重ねないといけないのです。面倒で、ついつい分厚く塗ってしまい、こんなことになってしまいました
 。
。
まだら模様です・・・
 。本当は「透明」という色を何度も塗ると少し濃い色になっていい感じになるはずだったのですが、一度目に塗ったときにあまりに色が薄かったので、面倒になり「透(すき)」という濃い目の色をしかも分厚く塗ってしまったのです
。本当は「透明」という色を何度も塗ると少し濃い色になっていい感じになるはずだったのですが、一度目に塗ったときにあまりに色が薄かったので、面倒になり「透(すき)」という濃い目の色をしかも分厚く塗ってしまったのです 。乾燥後、あまりにかっこ悪かったので、削ったのですが、もともと凹んでいる部分は、削っても塗装が取れず、これ以上削ると籐自体が削れてしまいそうだったので、あきらめてまだら模様を選択することになったわけです。できあがれば、まあこれはこれでええっか~という感じです。では拡大写真
。乾燥後、あまりにかっこ悪かったので、削ったのですが、もともと凹んでいる部分は、削っても塗装が取れず、これ以上削ると籐自体が削れてしまいそうだったので、あきらめてまだら模様を選択することになったわけです。できあがれば、まあこれはこれでええっか~という感じです。では拡大写真 。
。
中央の黒い部分は、前回エギのアワビシートをあしらってみたのですが、わが息子に「かっこ悪い」と不評でしたので、それを取り除きました。そして、かわりに継ぎ口の糸巻き部とともに金粉を降りかけてみましたが、ちょっと全体にかけ過ぎてどこかのケバいおねえちゃんのネイルのようになってしまいました
 。まあ、これも実験ということでOKでしょう。全体的にまだ少しデコボコはありますが、まあドシロートの1作目はこんなもんでしょう
。まあ、これも実験ということでOKでしょう。全体的にまだ少しデコボコはありますが、まあドシロートの1作目はこんなもんでしょう 。
。
こちらは継ぎ口部分です。やはり金粉をいっぱい付けたので、ピカピカ
 のネイル状態です。拡大写真はこちら
のネイル状態です。拡大写真はこちら 。
。
糸巻きは今回かなり細い糸を使いましたので、盛り上がりも少なくいい感じにできました。ただ、細い糸は巻くのも時間がかかるので面倒です。途中でロッドモーターで竿を回しながら巻く方法を試すと、結構簡単に巻けるようになりましたので、次回からはその方法でいきます
 。
。最後に穂先です。「竹で穂先を作ってやる」、これが今回の改造の大きなテーマでした。ホームセンターで真竹?の平たい割竹を一本購入(確か150円程度)。それを削って作りました
 。
。
まずは竹を細く切り、そしてカンナで四角柱を作り、さらに強い表皮部分は残すようにカンナを入れてテーパーをつけた四角錐にします。そして角を取って八角錐に、そこからはヤスリを使い円錐形に、そしてドリルに尻部を挟み、回しながら紙やすりで仕上げていきます。途中火入れを何度もしながらまっすぐにしていきます。まだほんの少し曲がっていますが、OKということにしておきましょう。何とかできましたが、穂先作りはとても大変な作業でした(でも楽しい・・・
 )。
)。竿作り全体を通じての感想は、とにかくとても面倒で根気のいる作業の連続でした。ただ仕上がった時には、達成感と満足感が満タンでした。問題はここからです・・・継ぎ口の部分は調子に乗って削りすぎて、かなり薄いんです。なので、実釣で「ポキッ」っといかないように願うばかりです
 。
。 タグ :竿2号
2012年01月18日
玉網と玉の柄の自作
1月18日(水)
気合を入れて、玉網と玉の柄一気に作ってしまいました 。
。

枠はゆっくり炙りながら曲げないといけないので、最初にトライした時は強く曲げ過ぎて折れたり 、焦げてしまったりしましたが
、焦げてしまったりしましたが 、直径7~8mm程度の細めの竹を使い、慎重にやるとうまくいきました。籐を巻いている部分の内側にはパテを埋め、またエポキシで固めて更に強化しました。かなり頑丈にできました。
、直径7~8mm程度の細めの竹を使い、慎重にやるとうまくいきました。籐を巻いている部分の内側にはパテを埋め、またエポキシで固めて更に強化しました。かなり頑丈にできました。
網を枠に編んで行くいくのに針のようなものが必要ですが、ちょうど良いサイズの針がなかったので、糸の先を瞬間接着剤で固めてみるとバッチリ 。網はケチって600円くらいの安物にしてしまいましたが、せっかくなのでヘラ用の普通のやつにすればよかったです。でも網だけで5000円くらいするんです
。網はケチって600円くらいの安物にしてしまいましたが、せっかくなのでヘラ用の普通のやつにすればよかったです。でも網だけで5000円くらいするんです 。いくらなんでも高すぎるでしょ
。いくらなんでも高すぎるでしょ 。
。
さて、玉の柄ですが、握り手は木を削って作ってみました(上部の差し込み口は上の写真に写ってます)。

ちょうど使えそうな円筒型の木材をコーナンで見つけたので、穴は竹のサイズに合わせて大きくし、竹も少し削って調整、木工ボンドで接着。外側はカンナで大まかに削り、ヤスリで仕上げ。水性絵具で色付けをして、ウレタンで塗装しました。糸や籐を巻くのとはまた違った雰囲気になります 。
。
思ったよりうまくできました 。まだいろいろと作りたいものがあるのですが、まずは一昨日の竿とあわせて使ってみます(竿の曲がりが不安
。まだいろいろと作りたいものがあるのですが、まずは一昨日の竿とあわせて使ってみます(竿の曲がりが不安 )。
)。
気合を入れて、玉網と玉の柄一気に作ってしまいました
 。
。
枠はゆっくり炙りながら曲げないといけないので、最初にトライした時は強く曲げ過ぎて折れたり
 、焦げてしまったりしましたが
、焦げてしまったりしましたが 、直径7~8mm程度の細めの竹を使い、慎重にやるとうまくいきました。籐を巻いている部分の内側にはパテを埋め、またエポキシで固めて更に強化しました。かなり頑丈にできました。
、直径7~8mm程度の細めの竹を使い、慎重にやるとうまくいきました。籐を巻いている部分の内側にはパテを埋め、またエポキシで固めて更に強化しました。かなり頑丈にできました。網を枠に編んで行くいくのに針のようなものが必要ですが、ちょうど良いサイズの針がなかったので、糸の先を瞬間接着剤で固めてみるとバッチリ
 。網はケチって600円くらいの安物にしてしまいましたが、せっかくなのでヘラ用の普通のやつにすればよかったです。でも網だけで5000円くらいするんです
。網はケチって600円くらいの安物にしてしまいましたが、せっかくなのでヘラ用の普通のやつにすればよかったです。でも網だけで5000円くらいするんです 。いくらなんでも高すぎるでしょ
。いくらなんでも高すぎるでしょ 。
。さて、玉の柄ですが、握り手は木を削って作ってみました(上部の差し込み口は上の写真に写ってます)。

ちょうど使えそうな円筒型の木材をコーナンで見つけたので、穴は竹のサイズに合わせて大きくし、竹も少し削って調整、木工ボンドで接着。外側はカンナで大まかに削り、ヤスリで仕上げ。水性絵具で色付けをして、ウレタンで塗装しました。糸や籐を巻くのとはまた違った雰囲気になります
 。
。思ったよりうまくできました
 。まだいろいろと作りたいものがあるのですが、まずは一昨日の竿とあわせて使ってみます(竿の曲がりが不安
。まだいろいろと作りたいものがあるのですが、まずは一昨日の竿とあわせて使ってみます(竿の曲がりが不安 )。
)。 2012年01月16日
竿2号
1月16日(月)
今週の土曜も磯に行こうと思っていましたが、爆風の予報だったので、仕方なくあきらめました 。・・・ということで、今週もへらの管釣りへ
。・・・ということで、今週もへらの管釣りへ =3。
=3。
寒さ対策にこんなものを入手してみました。皆さんが使っているような高級ブランド品ではありませんが、組み立ても楽勝で(開けるだけ)、効果もばっちり、全然寒くなかったです。
へらはまだ始めたばかりなので、いろいろなエサや釣りパターンを順に試しているのですが、今回は完敗 。前回両グルテン(+ペレット付け)の底釣りで好調だったので(前々回は両ウドン、その前はセット釣り)、本日はエサはそのまま、宙釣りでやってみましたがダメ。結局、最後の方に底釣りに変えて、やっとこさ1枚。
。前回両グルテン(+ペレット付け)の底釣りで好調だったので(前々回は両ウドン、その前はセット釣り)、本日はエサはそのまま、宙釣りでやってみましたがダメ。結局、最後の方に底釣りに変えて、やっとこさ1枚。

サイズは35cm程度と結構よかったです。やはりこの季節、チヌと同じように底なのでしょうか?宙でたくさん釣っている人もいるようなのですが・・・。まだまだ修行が足りません 。
。
実はもう1枚かけたのですが、やりとりを必要以上にやっていると水面でバラしてしまいました。やはり、手作り竿1号は半分ペナペナのグラスソリッドで柔らかすぎてなかなか浮いて来ないし、手前の桟橋下に突っ込まれるし・・・ 。
。
早急に2号の製作が必要でしょ・・・ ということでがんばってみました
ということでがんばってみました 。
。

今回、握り手は籐を巻いてみました。全部籐にしようかと思いましたが、足りなかったので、中央部は糸で巻き、実験的にエギ用のアワビシートを切って貼り、その上から塗装してみました。

3本継ぎの8.5尺程度ですが、穂先はカーボン、穂持ちと手元は竹です。穂先は手元に収納できるように竹の節を抜きました(鉄棒でロングドリルを作りました)。塗装は、まず握り手と継ぎ口をエポキシで固め、そして全体にウレタン塗装を2度しました。次回はこの竿でがんばってみます 。
。
勢いで、玉枠の作業も進めました。こちらももう少しで完成です。

こちらに籐を使ってしまったので、握り手に不足してしまいました 。
。
今週の土曜も磯に行こうと思っていましたが、爆風の予報だったので、仕方なくあきらめました
 。・・・ということで、今週もへらの管釣りへ
。・・・ということで、今週もへらの管釣りへ =3。
=3。寒さ対策にこんなものを入手してみました。皆さんが使っているような高級ブランド品ではありませんが、組み立ても楽勝で(開けるだけ)、効果もばっちり、全然寒くなかったです。
へらはまだ始めたばかりなので、いろいろなエサや釣りパターンを順に試しているのですが、今回は完敗
 。前回両グルテン(+ペレット付け)の底釣りで好調だったので(前々回は両ウドン、その前はセット釣り)、本日はエサはそのまま、宙釣りでやってみましたがダメ。結局、最後の方に底釣りに変えて、やっとこさ1枚。
。前回両グルテン(+ペレット付け)の底釣りで好調だったので(前々回は両ウドン、その前はセット釣り)、本日はエサはそのまま、宙釣りでやってみましたがダメ。結局、最後の方に底釣りに変えて、やっとこさ1枚。
サイズは35cm程度と結構よかったです。やはりこの季節、チヌと同じように底なのでしょうか?宙でたくさん釣っている人もいるようなのですが・・・。まだまだ修行が足りません
 。
。実はもう1枚かけたのですが、やりとりを必要以上にやっていると水面でバラしてしまいました。やはり、手作り竿1号は半分ペナペナのグラスソリッドで柔らかすぎてなかなか浮いて来ないし、手前の桟橋下に突っ込まれるし・・・
 。
。早急に2号の製作が必要でしょ・・・
 ということでがんばってみました
ということでがんばってみました 。
。
今回、握り手は籐を巻いてみました。全部籐にしようかと思いましたが、足りなかったので、中央部は糸で巻き、実験的にエギ用のアワビシートを切って貼り、その上から塗装してみました。

3本継ぎの8.5尺程度ですが、穂先はカーボン、穂持ちと手元は竹です。穂先は手元に収納できるように竹の節を抜きました(鉄棒でロングドリルを作りました)。塗装は、まず握り手と継ぎ口をエポキシで固め、そして全体にウレタン塗装を2度しました。次回はこの竿でがんばってみます
 。
。勢いで、玉枠の作業も進めました。こちらももう少しで完成です。

こちらに籐を使ってしまったので、握り手に不足してしまいました
 。
。2012年01月03日
竿作り
1月3日(火)
前回の記事でヘラブナに使った竿ですが、自作第1号ということで、簡単にするために半分は竹、半分はグラスソリッドという2本継ぎのシンプルなものにしました。長さは約8尺(2.4m)。わたしの使用する竹はこんなやつです。

100円ショップやホームセンターで売っている、超安価なやつです・・・ 。こんな中から極端に節が飛び出てないやつ、適当な太さ、干からびてない竹、などの基準で選定します。そして節から出ていた枝の後を彫刻刀で削り、火入れ(台所のコンロ)して、曲げを直していきます。子供の頃にやった竹ひご飛行機を作る要領です(こちらは太いですけど)。炙り過ぎると突然焦げる
。こんな中から極端に節が飛び出てないやつ、適当な太さ、干からびてない竹、などの基準で選定します。そして節から出ていた枝の後を彫刻刀で削り、火入れ(台所のコンロ)して、曲げを直していきます。子供の頃にやった竹ひご飛行機を作る要領です(こちらは太いですけど)。炙り過ぎると突然焦げる ので、ゆっくり火入れします。そしてある程度まっすぐになったら、継ぎの口を作ります。
ので、ゆっくり火入れします。そしてある程度まっすぐになったら、継ぎの口を作ります。

まず、タコ糸などを巻いて補強しておいてから(しないと割れる)、ドリルの刃を手やペンチで挟んで、竹の方をクリクリと回しながらゆっくり削っていきます。ドリルの刃の直径は少しずつ大きくしていきます(根気がいる作業です)。予定の大きさに近づいたら(竹をギリギリまで薄くする感じです)後はヤスリで調整します。込み口が完成したら、タコ糸をはずして、口の方から細めの糸を巻いていきます。

さし込む方は、この穴の大きさにあわせて少しずつテストしながら削っていけばOKです。
次に握り手を作っていきます。新聞紙を切って竹に巻いていきます。ヤスリで形は整えます。意外と簡単にこんな風にできます。

そして、今度は尻側から糸を巻いて行きます。少しかっこよくするために最後の部分はエンジ色の糸を巻きました 。
。

こちらはまだ2回塗りで、磨いていませんが、込み口と穂先です。穂先は120cmのグラスソリッドをマジックで黒に塗り、ウレタン塗装しています。

握り手は中途半端にテカテカですが、あと一度厚めに塗ってから、ヤスリとコンパウンドで磨いて終了予定です。

釣って曲がるとこんな感じになりました。 。
。

グラスソリッドはちょっとやわらかすぎるので、穂先側120cmの半分くらいは細い竹にして先のみグラスにすることを検討中です・・・ 。すでに第2号竿の仕込みもやっています・・・
。すでに第2号竿の仕込みもやっています・・・ 。おまけに玉枠も・・・
。おまけに玉枠も・・・ 。
。
あ~、明日から仕事です。おまけにいきなり東京じゃ・・・ ・・・(でも、釣具屋にも行ける・・・
・・・(でも、釣具屋にも行ける・・・ )。
)。
前回の記事でヘラブナに使った竿ですが、自作第1号ということで、簡単にするために半分は竹、半分はグラスソリッドという2本継ぎのシンプルなものにしました。長さは約8尺(2.4m)。わたしの使用する竹はこんなやつです。

100円ショップやホームセンターで売っている、超安価なやつです・・・
 。こんな中から極端に節が飛び出てないやつ、適当な太さ、干からびてない竹、などの基準で選定します。そして節から出ていた枝の後を彫刻刀で削り、火入れ(台所のコンロ)して、曲げを直していきます。子供の頃にやった竹ひご飛行機を作る要領です(こちらは太いですけど)。炙り過ぎると突然焦げる
。こんな中から極端に節が飛び出てないやつ、適当な太さ、干からびてない竹、などの基準で選定します。そして節から出ていた枝の後を彫刻刀で削り、火入れ(台所のコンロ)して、曲げを直していきます。子供の頃にやった竹ひご飛行機を作る要領です(こちらは太いですけど)。炙り過ぎると突然焦げる ので、ゆっくり火入れします。そしてある程度まっすぐになったら、継ぎの口を作ります。
ので、ゆっくり火入れします。そしてある程度まっすぐになったら、継ぎの口を作ります。
まず、タコ糸などを巻いて補強しておいてから(しないと割れる)、ドリルの刃を手やペンチで挟んで、竹の方をクリクリと回しながらゆっくり削っていきます。ドリルの刃の直径は少しずつ大きくしていきます(根気がいる作業です)。予定の大きさに近づいたら(竹をギリギリまで薄くする感じです)後はヤスリで調整します。込み口が完成したら、タコ糸をはずして、口の方から細めの糸を巻いていきます。

さし込む方は、この穴の大きさにあわせて少しずつテストしながら削っていけばOKです。
次に握り手を作っていきます。新聞紙を切って竹に巻いていきます。ヤスリで形は整えます。意外と簡単にこんな風にできます。

そして、今度は尻側から糸を巻いて行きます。少しかっこよくするために最後の部分はエンジ色の糸を巻きました
 。
。
こちらはまだ2回塗りで、磨いていませんが、込み口と穂先です。穂先は120cmのグラスソリッドをマジックで黒に塗り、ウレタン塗装しています。

握り手は中途半端にテカテカですが、あと一度厚めに塗ってから、ヤスリとコンパウンドで磨いて終了予定です。

釣って曲がるとこんな感じになりました。
 。
。
グラスソリッドはちょっとやわらかすぎるので、穂先側120cmの半分くらいは細い竹にして先のみグラスにすることを検討中です・・・
 。すでに第2号竿の仕込みもやっています・・・
。すでに第2号竿の仕込みもやっています・・・ 。おまけに玉枠も・・・
。おまけに玉枠も・・・ 。
。あ~、明日から仕事です。おまけにいきなり東京じゃ・・・
 ・・・(でも、釣具屋にも行ける・・・
・・・(でも、釣具屋にも行ける・・・ )。
)。 タグ :竿1号
2011年12月26日
ロッドモーター
12月26日(月)
この週末にこんなん作ってしまいました 。以前、ガイドの補修をした際にエポキシ系接着剤で固めたのですが、乾燥するまでの間に接着剤が垂れてきてきれいに仕上がりませんでした。それもあって、ロッドモーターを作ってみました。これがあると、修理や製作をやる気になります
。以前、ガイドの補修をした際にエポキシ系接着剤で固めたのですが、乾燥するまでの間に接着剤が垂れてきてきれいに仕上がりませんでした。それもあって、ロッドモーターを作ってみました。これがあると、修理や製作をやる気になります 。
。
まずロッドモーターですので、1分間に10~15回転程度でゆっくりと回るモーターが必要ですが、インターネットで調べていると、モーターは日本電産サーボのモーターを皆さん使っているようです。1個1000円ほどとのことなので、東京で仕事ついでに秋葉原まで買いに行ったのですが、震災以降商品が入ってこないとのこと 。店員さんに聞くと、電池でゆっくりと動く直流モーターならあるとのこと。電池4つで1分間に60回転くらい回るモーターということで、早すぎるなと思ったのですが、電池を2個にするとゆっくりになり、1分間に12~15回転程度と理想的でした。なんと1個200円
。店員さんに聞くと、電池でゆっくりと動く直流モーターならあるとのこと。電池4つで1分間に60回転くらい回るモーターということで、早すぎるなと思ったのですが、電池を2個にするとゆっくりになり、1分間に12~15回転程度と理想的でした。なんと1個200円 だったので、思わず2個購入。
だったので、思わず2個購入。
あとはホームセンターで、90cm×15cm程度の木材と水道管キャップ、ネジ、薄いゴムを買って適当に切って組み立てて完了です。大小の2本一度に乾かせるようにしました。木の丸棒で実験してみましたが、スムーズに動きます。大成功 。
。
釣りの方ですが、土曜日に少し時間ができたので、先週も行ったヘラブナの管理池に行ったのですが、な・な・な・なんと丸ボウズ 。でも周りの人を見ていると、エサが違う・・・
。でも周りの人を見ていると、エサが違う・・・ 。次は研究しなおして、作戦変更です。ちなみに、私以外にもボウズの人は何人もいたようなんで、いまは余程活性が悪いのか、それともこの季節はこんなもんなのかは不明です
。次は研究しなおして、作戦変更です。ちなみに、私以外にもボウズの人は何人もいたようなんで、いまは余程活性が悪いのか、それともこの季節はこんなもんなのかは不明です 。
。
ということで、ホームセンターへ買い物に・・・。そして気付くと、クリスマスにこんなことをやっていました 。
。
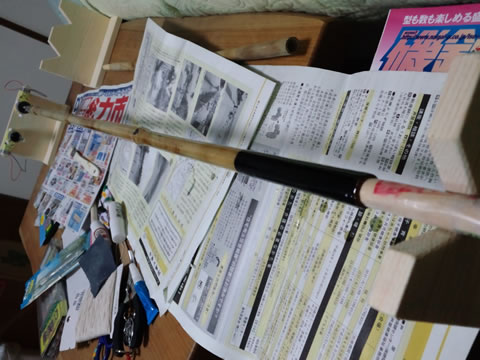
もう、最終段階ですが、竿掛けです。ひと束(10本ほど入り)300円程度で竹を買ってきて、炙ってまっすぐにして、ドリルの刃を手に持ってまわしてそーっと穴をあけ、口に糸を巻いて、エポキシで強化、ウレタン塗装をかけて、乾燥させているところです。これは結構うまくいきましたので、その内、竿も作ってみようかと・・・ 。
。
時間があれば釣り納めに行きたいところですが、仕事もこの年末になって急に忙しくなったりして、今年はもう時間がないかもしれません。今年の釣りを近々振り返ってみようと思います。
【追記】
とりあえず出来上がったので写真アップしときます。本当は、3度塗りするつもりでしたが、面倒になったので2度塗りで終了。ハケの毛が1本、塗装に埋まってしまいました 。まあ、いっか~
。まあ、いっか~ 。
。

この週末にこんなん作ってしまいました
 。以前、ガイドの補修をした際にエポキシ系接着剤で固めたのですが、乾燥するまでの間に接着剤が垂れてきてきれいに仕上がりませんでした。それもあって、ロッドモーターを作ってみました。これがあると、修理や製作をやる気になります
。以前、ガイドの補修をした際にエポキシ系接着剤で固めたのですが、乾燥するまでの間に接着剤が垂れてきてきれいに仕上がりませんでした。それもあって、ロッドモーターを作ってみました。これがあると、修理や製作をやる気になります 。
。まずロッドモーターですので、1分間に10~15回転程度でゆっくりと回るモーターが必要ですが、インターネットで調べていると、モーターは日本電産サーボのモーターを皆さん使っているようです。1個1000円ほどとのことなので、東京で仕事ついでに秋葉原まで買いに行ったのですが、震災以降商品が入ってこないとのこと
 。店員さんに聞くと、電池でゆっくりと動く直流モーターならあるとのこと。電池4つで1分間に60回転くらい回るモーターということで、早すぎるなと思ったのですが、電池を2個にするとゆっくりになり、1分間に12~15回転程度と理想的でした。なんと1個200円
。店員さんに聞くと、電池でゆっくりと動く直流モーターならあるとのこと。電池4つで1分間に60回転くらい回るモーターということで、早すぎるなと思ったのですが、電池を2個にするとゆっくりになり、1分間に12~15回転程度と理想的でした。なんと1個200円 だったので、思わず2個購入。
だったので、思わず2個購入。あとはホームセンターで、90cm×15cm程度の木材と水道管キャップ、ネジ、薄いゴムを買って適当に切って組み立てて完了です。大小の2本一度に乾かせるようにしました。木の丸棒で実験してみましたが、スムーズに動きます。大成功
 。
。釣りの方ですが、土曜日に少し時間ができたので、先週も行ったヘラブナの管理池に行ったのですが、な・な・な・なんと丸ボウズ
 。でも周りの人を見ていると、エサが違う・・・
。でも周りの人を見ていると、エサが違う・・・ 。次は研究しなおして、作戦変更です。ちなみに、私以外にもボウズの人は何人もいたようなんで、いまは余程活性が悪いのか、それともこの季節はこんなもんなのかは不明です
。次は研究しなおして、作戦変更です。ちなみに、私以外にもボウズの人は何人もいたようなんで、いまは余程活性が悪いのか、それともこの季節はこんなもんなのかは不明です 。
。ということで、ホームセンターへ買い物に・・・。そして気付くと、クリスマスにこんなことをやっていました
 。
。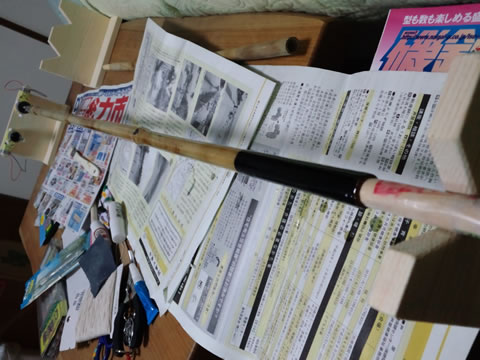
もう、最終段階ですが、竿掛けです。ひと束(10本ほど入り)300円程度で竹を買ってきて、炙ってまっすぐにして、ドリルの刃を手に持ってまわしてそーっと穴をあけ、口に糸を巻いて、エポキシで強化、ウレタン塗装をかけて、乾燥させているところです。これは結構うまくいきましたので、その内、竿も作ってみようかと・・・
 。
。時間があれば釣り納めに行きたいところですが、仕事もこの年末になって急に忙しくなったりして、今年はもう時間がないかもしれません。今年の釣りを近々振り返ってみようと思います。
【追記】
とりあえず出来上がったので写真アップしときます。本当は、3度塗りするつもりでしたが、面倒になったので2度塗りで終了。ハケの毛が1本、塗装に埋まってしまいました
 。まあ、いっか~
。まあ、いっか~ 。
。
2011年10月10日
ロッドスタンド製作
10月10日(月)
気付くとロッドだらけ・・・ 、そんな人も多いことでしょう。わたしももちろん同じです
、そんな人も多いことでしょう。わたしももちろん同じです 。
。
以前からロッドスタンドを買おうかなと思っていたのですが、いまいち気にいるのもないし、いいやつは高いし・・・。ということで、作ってしまうことにしました 。
。

適当に製図しましたが、思ったよりうまくいきました 。ただ、失敗は木の材質が柔らかすぎて、加工がかえって大変でした。
。ただ、失敗は木の材質が柔らかすぎて、加工がかえって大変でした。
このスタンドはロッドが14本入ります。高さは70cm、幅20cm、奥行きは30cmです。まあホームセンターで売っている木材の長さが30、60、90cm、幅が5、10、20cmという感じなので、それを最小限の加工で済ませるように利用するとこんな感じになりました。90の板は70cmと20cmに切って使っています。あとはロッドが接触する部分にコルクを貼ったのとアルミの棒を支えに使っています。仕上げはオイルフィニッシュ、ナチュラルです。
このロッドスタンドは2つ同時に作りました。合計で28本(これでも足らないかも・・・ )。本当は大きいのを1つ作ってもよかったのですが、2つに分けた方が収納の自由度が高いのでそうしました。こんな感じになります。
)。本当は大きいのを1つ作ってもよかったのですが、2つに分けた方が収納の自由度が高いのでそうしました。こんな感じになります。
まずは背中あわせ。

次に向かえあわせ。

そして横並び。これはかなりコンパクトに28本収納できます。

木材だけでなく、不足している工具なんかも買ったので、ロッドスタンドを購入するのと大して金額はかわらなくなってしまいましたが、自分の好きなように作れるところと愛着がわくところがいいところです 。
。
気付くとロッドだらけ・・・
 、そんな人も多いことでしょう。わたしももちろん同じです
、そんな人も多いことでしょう。わたしももちろん同じです 。
。以前からロッドスタンドを買おうかなと思っていたのですが、いまいち気にいるのもないし、いいやつは高いし・・・。ということで、作ってしまうことにしました
 。
。
適当に製図しましたが、思ったよりうまくいきました
 。ただ、失敗は木の材質が柔らかすぎて、加工がかえって大変でした。
。ただ、失敗は木の材質が柔らかすぎて、加工がかえって大変でした。このスタンドはロッドが14本入ります。高さは70cm、幅20cm、奥行きは30cmです。まあホームセンターで売っている木材の長さが30、60、90cm、幅が5、10、20cmという感じなので、それを最小限の加工で済ませるように利用するとこんな感じになりました。90の板は70cmと20cmに切って使っています。あとはロッドが接触する部分にコルクを貼ったのとアルミの棒を支えに使っています。仕上げはオイルフィニッシュ、ナチュラルです。
このロッドスタンドは2つ同時に作りました。合計で28本(これでも足らないかも・・・
 )。本当は大きいのを1つ作ってもよかったのですが、2つに分けた方が収納の自由度が高いのでそうしました。こんな感じになります。
)。本当は大きいのを1つ作ってもよかったのですが、2つに分けた方が収納の自由度が高いのでそうしました。こんな感じになります。まずは背中あわせ。

次に向かえあわせ。

そして横並び。これはかなりコンパクトに28本収納できます。

木材だけでなく、不足している工具なんかも買ったので、ロッドスタンドを購入するのと大して金額はかわらなくなってしまいましたが、自分の好きなように作れるところと愛着がわくところがいいところです
 。
。 タグ :ロッドスタンド
2011年09月04日
暇つぶしPartⅡ
9月4日(日)
少しギックリ腰の状況も良くなってきましたが、まだ出歩けるほどではありません。でも暇なので、手近にあるものでジグ再生の続きをしてみました。
まずはアイアンプレートもアルミテープを貼りました。腹の部分はジグの時同様に鉄ヤスリを押しつけ模様を入れましたが、横腹や背の部分はツルツルのままにしました。上部の平らな部分は、ゴールドがかっちょいいので、そのままにしました。そして、色付けはこどもの油性マジック 。ピンク色も欲しかったのですが、ピンク色はもうでない・・・
。ピンク色も欲しかったのですが、ピンク色はもうでない・・・ 。なので、青と水色と黄色を使って色を付けてみました(青色も固まりかけてて塗りにくすぎ・・・
。なので、青と水色と黄色を使って色を付けてみました(青色も固まりかけてて塗りにくすぎ・・・ )。
)。
ジグのムーチョはエアスプレー缶の青を使って吹いてみましたが、霧の範囲が大きすぎて、小さなジグに色を塗るのはとてもやりにくいです。しかたないので、こちらも油性マジックで少し加筆。横腹に黄色のラインを入れ、お腹はオレンジ色に。
するとこんな感じになりました。まずお腹側から。

そして背中側から。

このあとは、必殺ケイムラカラーを塗って、ウレタンドブ付けすれば終了です。
やはり、仕上がりは油性マジックではムラっぽくなってしまいますね~。ジグは基本の青色にカラースプレーを使った分、まだ少しましです。こんなことをやっているとプラモ用のエアブラシが欲しくなってきました。その内、買ってしまっているかもしれません・・・ 。
。
【後日の追記】
息子のウマ君が、「ぼくも色を塗りたい」って・・・ 。ならば、また磨いてみようとムーチョをあと2本とりだしました。
。ならば、また磨いてみようとムーチョをあと2本とりだしました。

慣れてしまったので、あっという間の作業でした。アルミテープにウロコ型を付けるのは、鉄やすりよりも、このデザインナイフの持ち手のところの方が丸くて簡単だということが判明 。
。
ウレタンのドブ漬けをする予定でしたが、腰が痛くて買いに行けなかったので、家にあったハケで塗るタイプを3度ほど重ね塗りして仕上げました。最終的にはこんな感じになりました。

わかめのふりをしたジグがありますが、実は「ものは試し」にスプレーをすると全体に色が広がったので、やけくそで全面に塗ってしまいました 。でも、これでも釣れるかも・・・
。でも、これでも釣れるかも・・・ 。ウマ君は赤いやつを製作
。ウマ君は赤いやつを製作 。でもケイムラ(シンナー系なので、塗ると塗料が少し溶ける)を塗ると予定よりも赤色が広がってしまったらしくちょっとご不満の様子
。でもケイムラ(シンナー系なので、塗ると塗料が少し溶ける)を塗ると予定よりも赤色が広がってしまったらしくちょっとご不満の様子 。わたしのお気に入りは最後に作った一番下の背中が赤系のものです(腹は緑系)。油性マジックだけでも結構それらしくできるもんです
。わたしのお気に入りは最後に作った一番下の背中が赤系のものです(腹は緑系)。油性マジックだけでも結構それらしくできるもんです 。
。
少しギックリ腰の状況も良くなってきましたが、まだ出歩けるほどではありません。でも暇なので、手近にあるものでジグ再生の続きをしてみました。
まずはアイアンプレートもアルミテープを貼りました。腹の部分はジグの時同様に鉄ヤスリを押しつけ模様を入れましたが、横腹や背の部分はツルツルのままにしました。上部の平らな部分は、ゴールドがかっちょいいので、そのままにしました。そして、色付けはこどもの油性マジック
 。ピンク色も欲しかったのですが、ピンク色はもうでない・・・
。ピンク色も欲しかったのですが、ピンク色はもうでない・・・ 。なので、青と水色と黄色を使って色を付けてみました(青色も固まりかけてて塗りにくすぎ・・・
。なので、青と水色と黄色を使って色を付けてみました(青色も固まりかけてて塗りにくすぎ・・・ )。
)。ジグのムーチョはエアスプレー缶の青を使って吹いてみましたが、霧の範囲が大きすぎて、小さなジグに色を塗るのはとてもやりにくいです。しかたないので、こちらも油性マジックで少し加筆。横腹に黄色のラインを入れ、お腹はオレンジ色に。
するとこんな感じになりました。まずお腹側から。

そして背中側から。

このあとは、必殺ケイムラカラーを塗って、ウレタンドブ付けすれば終了です。
やはり、仕上がりは油性マジックではムラっぽくなってしまいますね~。ジグは基本の青色にカラースプレーを使った分、まだ少しましです。こんなことをやっているとプラモ用のエアブラシが欲しくなってきました。その内、買ってしまっているかもしれません・・・
 。
。【後日の追記】
息子のウマ君が、「ぼくも色を塗りたい」って・・・
 。ならば、また磨いてみようとムーチョをあと2本とりだしました。
。ならば、また磨いてみようとムーチョをあと2本とりだしました。
慣れてしまったので、あっという間の作業でした。アルミテープにウロコ型を付けるのは、鉄やすりよりも、このデザインナイフの持ち手のところの方が丸くて簡単だということが判明
 。
。ウレタンのドブ漬けをする予定でしたが、腰が痛くて買いに行けなかったので、家にあったハケで塗るタイプを3度ほど重ね塗りして仕上げました。最終的にはこんな感じになりました。

わかめのふりをしたジグがありますが、実は「ものは試し」にスプレーをすると全体に色が広がったので、やけくそで全面に塗ってしまいました
 。でも、これでも釣れるかも・・・
。でも、これでも釣れるかも・・・ 。ウマ君は赤いやつを製作
。ウマ君は赤いやつを製作 。でもケイムラ(シンナー系なので、塗ると塗料が少し溶ける)を塗ると予定よりも赤色が広がってしまったらしくちょっとご不満の様子
。でもケイムラ(シンナー系なので、塗ると塗料が少し溶ける)を塗ると予定よりも赤色が広がってしまったらしくちょっとご不満の様子 。わたしのお気に入りは最後に作った一番下の背中が赤系のものです(腹は緑系)。油性マジックだけでも結構それらしくできるもんです
。わたしのお気に入りは最後に作った一番下の背中が赤系のものです(腹は緑系)。油性マジックだけでも結構それらしくできるもんです 。
。 タグ :ジグ再生
2011年09月03日
暇つぶし
9月3日(土)
今週末は台風 で釣りは無理だと思ったので、週末の暇つぶしにジグでも再生させるかと・・・。とりあえず実験に3つだけ塗装を落として準備してみようと、100円ショップで鉄ヤスリと紙ヤスリ他を入手。鉄ヤスリでまず磨き、紙ヤスリ(600番)は水につけながらざっと磨いてみました
で釣りは無理だと思ったので、週末の暇つぶしにジグでも再生させるかと・・・。とりあえず実験に3つだけ塗装を落として準備してみようと、100円ショップで鉄ヤスリと紙ヤスリ他を入手。鉄ヤスリでまず磨き、紙ヤスリ(600番)は水につけながらざっと磨いてみました 。
。

上から撃投ジグ、ムーチョルチア、アイアンプレートです。撃投ジグはわたしの定番。色を塗るために白地は残してみました。ムーチョルチアはみんな釣っているから釣れるはずだ~と思いながら、投げ続けているジグです(未だ釣果なし )。こちらは白地も落としてみました。そして、アイアンプレートは今期絶好調のバイブレーションです
)。こちらは白地も落としてみました。そして、アイアンプレートは今期絶好調のバイブレーションです 。色を剥がすとゴールドと銀なので、このままでも釣れそうです。
。色を剥がすとゴールドと銀なので、このままでも釣れそうです。
さて、次にこれも100円ショップで仕入れたアルミテープ、台所用品コーナーにあります。

ネットで調べているとこれをジグに張り付けるとよく光るらしいです。少し伸びるのか、意外と貼りやすいです。指の腹で伸ばしながら貼っていきました。

ピカピカです 。でもこれだけだと淋しいので、少しウロコ模様を付けて光が乱反射するようにしてみようと鉄ヤスリを押しつけて模様を付けました。以前、ルアー製作の記事か何かで見たことがあったので、やってみたのですが、これがかなりGOODです
。でもこれだけだと淋しいので、少しウロコ模様を付けて光が乱反射するようにしてみようと鉄ヤスリを押しつけて模様を付けました。以前、ルアー製作の記事か何かで見たことがあったので、やってみたのですが、これがかなりGOODです 。
。

ここまで順調にすすんできたので、波に乗ってきたところでしたが・・・
「ビリ・ビリ・・・ 」
」
・・・・・・・

・・・・・
またまたやってしまいました 。ぎっくり腰再発。フローリングの床に座りながら、ちょっと横を向いてハサミを取って、アルミテープを切ろうとしただけなんです・・・
。ぎっくり腰再発。フローリングの床に座りながら、ちょっと横を向いてハサミを取って、アルミテープを切ろうとしただけなんです・・・ 。
。
1年に1~2回はやっているので、完全にバキッと行く前に止める技は持っているんですが、今回はレベル2程度(レベル5がまったく動けない最悪のやつです)。2~3日は杖なしでは歩けない感じです。つまり、明日台風が去っても釣りに行けず、月曜や火曜に朝練に行こうと思っても行けないということです 。
。
せめてこのジグ再生の続きをしたいのですが、100円ショップにカラースプレーを買いに行くこともできないので、作業も進めることができません。
悲しいです 。
。
(でも、この週末、釣具屋に行って散在しなくてすみました 。)
。)
今週末は台風
 で釣りは無理だと思ったので、週末の暇つぶしにジグでも再生させるかと・・・。とりあえず実験に3つだけ塗装を落として準備してみようと、100円ショップで鉄ヤスリと紙ヤスリ他を入手。鉄ヤスリでまず磨き、紙ヤスリ(600番)は水につけながらざっと磨いてみました
で釣りは無理だと思ったので、週末の暇つぶしにジグでも再生させるかと・・・。とりあえず実験に3つだけ塗装を落として準備してみようと、100円ショップで鉄ヤスリと紙ヤスリ他を入手。鉄ヤスリでまず磨き、紙ヤスリ(600番)は水につけながらざっと磨いてみました 。
。
上から撃投ジグ、ムーチョルチア、アイアンプレートです。撃投ジグはわたしの定番。色を塗るために白地は残してみました。ムーチョルチアはみんな釣っているから釣れるはずだ~と思いながら、投げ続けているジグです(未だ釣果なし
 )。こちらは白地も落としてみました。そして、アイアンプレートは今期絶好調のバイブレーションです
)。こちらは白地も落としてみました。そして、アイアンプレートは今期絶好調のバイブレーションです 。色を剥がすとゴールドと銀なので、このままでも釣れそうです。
。色を剥がすとゴールドと銀なので、このままでも釣れそうです。さて、次にこれも100円ショップで仕入れたアルミテープ、台所用品コーナーにあります。

ネットで調べているとこれをジグに張り付けるとよく光るらしいです。少し伸びるのか、意外と貼りやすいです。指の腹で伸ばしながら貼っていきました。

ピカピカです
 。でもこれだけだと淋しいので、少しウロコ模様を付けて光が乱反射するようにしてみようと鉄ヤスリを押しつけて模様を付けました。以前、ルアー製作の記事か何かで見たことがあったので、やってみたのですが、これがかなりGOODです
。でもこれだけだと淋しいので、少しウロコ模様を付けて光が乱反射するようにしてみようと鉄ヤスリを押しつけて模様を付けました。以前、ルアー製作の記事か何かで見たことがあったので、やってみたのですが、これがかなりGOODです 。
。
ここまで順調にすすんできたので、波に乗ってきたところでしたが・・・
「ビリ・ビリ・・・
 」
」・・・・・・・


・・・・・
またまたやってしまいました
 。ぎっくり腰再発。フローリングの床に座りながら、ちょっと横を向いてハサミを取って、アルミテープを切ろうとしただけなんです・・・
。ぎっくり腰再発。フローリングの床に座りながら、ちょっと横を向いてハサミを取って、アルミテープを切ろうとしただけなんです・・・ 。
。1年に1~2回はやっているので、完全にバキッと行く前に止める技は持っているんですが、今回はレベル2程度(レベル5がまったく動けない最悪のやつです)。2~3日は杖なしでは歩けない感じです。つまり、明日台風が去っても釣りに行けず、月曜や火曜に朝練に行こうと思っても行けないということです
 。
。せめてこのジグ再生の続きをしたいのですが、100円ショップにカラースプレーを買いに行くこともできないので、作業も進めることができません。
悲しいです
 。
。(でも、この週末、釣具屋に行って散在しなくてすみました
 。)
。) タグ :ジグ再生
2011年02月11日
タモ立てとエサ掛け
2月11日(金)
本日は釣りに行く気満々で6時前に起きたのですが(エーッ・・・ )、携帯で天気予報を確認して、やっぱりもう一度寝ることにしました
)、携帯で天気予報を確認して、やっぱりもう一度寝ることにしました 。いくらなんでも寒すぎます
。いくらなんでも寒すぎます 。こんな日に釣りに行って風邪でも引いたらイヤなので、本日の釣りはあきらめました
。こんな日に釣りに行って風邪でも引いたらイヤなので、本日の釣りはあきらめました 。
。
といっても本日はウマ君もおらず暇なので、ホームセンターへ行って、材料を買ってきて、ちょっと細工してみました 。細工といっても、L字ステーを曲げ、穴のひとつをネジが通るように大きくしたのと、配管パイプを半分に切ったくらいです。あとは組み立てただけです。
。細工といっても、L字ステーを曲げ、穴のひとつをネジが通るように大きくしたのと、配管パイプを半分に切ったくらいです。あとは組み立てただけです。

「なんじゃこりゃぁ・・・ 」
」
もちろん配管工事をするつもりではありません 。先日、初磯でピトンの竿置きを使いましたが、これに刺し餌ケースを掛けるところが欲しいなと
。先日、初磯でピトンの竿置きを使いましたが、これに刺し餌ケースを掛けるところが欲しいなと ・・・おまけに磯で釣りをするとタモの置き場に困るので、傘立てのようなタモ立ても一緒にできないかなと考えていました。
・・・おまけに磯で釣りをするとタモの置き場に困るので、傘立てのようなタモ立ても一緒にできないかなと考えていました。
ネットで調べると、エサ掛けだけ買っても2000円以上します。タモ立てもイメージ通りのものを見つけましたが、さらに倍以上高い 。じゃあ、作ってやろうと思い、適当な部品を見つけて組み立てたわけです。もちろん金属は錆びにくいステンレスのものを選びました。
。じゃあ、作ってやろうと思い、適当な部品を見つけて組み立てたわけです。もちろん金属は錆びにくいステンレスのものを選びました。

大成功 。
。
配管パイプが灰色なのがちょっとだけダサいですけど、それ以外は結構いけてます 。耐久性もありそうです。もう少し、近くでお見せすると・・・。まずはエサ掛け。
。耐久性もありそうです。もう少し、近くでお見せすると・・・。まずはエサ掛け。

足を洗う釣り場の場合、バッカン掛けにも使えそうです。
そしてタモ立て。

なんだかいけそうでしょ 。これで1回分の渡船代は浮いたな・・・と
。これで1回分の渡船代は浮いたな・・・と 。
。
本日は釣りに行く気満々で6時前に起きたのですが(エーッ・・・
 )、携帯で天気予報を確認して、やっぱりもう一度寝ることにしました
)、携帯で天気予報を確認して、やっぱりもう一度寝ることにしました 。いくらなんでも寒すぎます
。いくらなんでも寒すぎます 。こんな日に釣りに行って風邪でも引いたらイヤなので、本日の釣りはあきらめました
。こんな日に釣りに行って風邪でも引いたらイヤなので、本日の釣りはあきらめました 。
。といっても本日はウマ君もおらず暇なので、ホームセンターへ行って、材料を買ってきて、ちょっと細工してみました
 。細工といっても、L字ステーを曲げ、穴のひとつをネジが通るように大きくしたのと、配管パイプを半分に切ったくらいです。あとは組み立てただけです。
。細工といっても、L字ステーを曲げ、穴のひとつをネジが通るように大きくしたのと、配管パイプを半分に切ったくらいです。あとは組み立てただけです。
「なんじゃこりゃぁ・・・
 」
」もちろん配管工事をするつもりではありません
 。先日、初磯でピトンの竿置きを使いましたが、これに刺し餌ケースを掛けるところが欲しいなと
。先日、初磯でピトンの竿置きを使いましたが、これに刺し餌ケースを掛けるところが欲しいなと ・・・おまけに磯で釣りをするとタモの置き場に困るので、傘立てのようなタモ立ても一緒にできないかなと考えていました。
・・・おまけに磯で釣りをするとタモの置き場に困るので、傘立てのようなタモ立ても一緒にできないかなと考えていました。ネットで調べると、エサ掛けだけ買っても2000円以上します。タモ立てもイメージ通りのものを見つけましたが、さらに倍以上高い
 。じゃあ、作ってやろうと思い、適当な部品を見つけて組み立てたわけです。もちろん金属は錆びにくいステンレスのものを選びました。
。じゃあ、作ってやろうと思い、適当な部品を見つけて組み立てたわけです。もちろん金属は錆びにくいステンレスのものを選びました。
大成功
 。
。配管パイプが灰色なのがちょっとだけダサいですけど、それ以外は結構いけてます
 。耐久性もありそうです。もう少し、近くでお見せすると・・・。まずはエサ掛け。
。耐久性もありそうです。もう少し、近くでお見せすると・・・。まずはエサ掛け。
足を洗う釣り場の場合、バッカン掛けにも使えそうです。
そしてタモ立て。

なんだかいけそうでしょ
 。これで1回分の渡船代は浮いたな・・・と
。これで1回分の渡船代は浮いたな・・・と 。
。 2011年02月08日
実釣会
2月7日(月)
昨日は昼からウマ君と管釣りトラウトに行ってきました 。磯遠征で腰を痛めていたので、軽い感じでやってきました。今回の主目的は、作ったルアーの実釣です
。磯遠征で腰を痛めていたので、軽い感じでやってきました。今回の主目的は、作ったルアーの実釣です (ドキドキ)。まず釣れるかどうかの前に泳ぐかどうかが心配でしたが・・・
(ドキドキ)。まず釣れるかどうかの前に泳ぐかどうかが心配でしたが・・・

結果はこの通り。半数はダメでした
 。特に第2作目のアカ金、黄緑、カラシ色の「ミノー三兄弟」は、気合を入れて作ったので悲しいです
。特に第2作目のアカ金、黄緑、カラシ色の「ミノー三兄弟」は、気合を入れて作ったので悲しいです 。横向きに寝そべりながら泳いでいました
。横向きに寝そべりながら泳いでいました 。ウマ君が作った「出目金」と「ボックス」はクルクル回るという状態
。ウマ君が作った「出目金」と「ボックス」はクルクル回るという状態 。「黒ッキー」は、傾きながら泳ぐという、まるで弱ったベイトのようでした
。「黒ッキー」は、傾きながら泳ぐという、まるで弱ったベイトのようでした 。予想外は、「まだらフィッシュ」。リップもありませんが(実質的な失敗作)、一番プリプリとおしりを振りながら泳ぎました
。予想外は、「まだらフィッシュ」。リップもありませんが(実質的な失敗作)、一番プリプリとおしりを振りながら泳ぎました 。
。
つまり、リップがついているもので泳いだのは、「レモンクッキー」だけ。もう少し研究しないといけないようです。次への課題です 。
。
次に釣れるかどうか・・・それぞれ数回ずつ投げました。まず一番期待度の高かった「シード」君。全然でした
 。今度はこれに羽根でもつけてみようかと・・・。「あっかんべぇ~」と「レモンクッキー」は泳ぎも静かなら、釣果も静か・・・沈黙でした
。今度はこれに羽根でもつけてみようかと・・・。「あっかんべぇ~」と「レモンクッキー」は泳ぎも静かなら、釣果も静か・・・沈黙でした 。「黒ッキー」と「まだらフィッシュ」は追いかけてくることはありましたが、やはり沈黙
。「黒ッキー」と「まだらフィッシュ」は追いかけてくることはありましたが、やはり沈黙 。普段でもスプーン以外はあまり釣れないので、致し方ありません。・・・で、最後に「錘スプーン」。釣れました。3投で3尾
。普段でもスプーン以外はあまり釣れないので、致し方ありません。・・・で、最後に「錘スプーン」。釣れました。3投で3尾 。これは爆釣スプーンかぁぁあああ
。これは爆釣スプーンかぁぁあああ って思って、4投目。
って思って、4投目。
「プチッ 」
」
・・・・・・・・・・ 。林の奥へ飛んで逝ってしまいました
。林の奥へ飛んで逝ってしまいました 。
。
家に帰り、早速大量生産しました 。今回は色をつけたり、ウレタンコートまでしちゃいました。2個だけ無加工にしてあります。ついでに木粉ねんどを使って、棒のやつもつくってみました。
。今回は色をつけたり、ウレタンコートまでしちゃいました。2個だけ無加工にしてあります。ついでに木粉ねんどを使って、棒のやつもつくってみました。

さて、これはどうでしょうか・・・ 。
。
ルアー作り初心者は、こういった簡単なものから始めるのがよさそうです
 。
。
昨日は昼からウマ君と管釣りトラウトに行ってきました
 。磯遠征で腰を痛めていたので、軽い感じでやってきました。今回の主目的は、作ったルアーの実釣です
。磯遠征で腰を痛めていたので、軽い感じでやってきました。今回の主目的は、作ったルアーの実釣です (ドキドキ)。まず釣れるかどうかの前に泳ぐかどうかが心配でしたが・・・
(ドキドキ)。まず釣れるかどうかの前に泳ぐかどうかが心配でしたが・・・
結果はこの通り。半数はダメでした

 。特に第2作目のアカ金、黄緑、カラシ色の「ミノー三兄弟」は、気合を入れて作ったので悲しいです
。特に第2作目のアカ金、黄緑、カラシ色の「ミノー三兄弟」は、気合を入れて作ったので悲しいです 。横向きに寝そべりながら泳いでいました
。横向きに寝そべりながら泳いでいました 。ウマ君が作った「出目金」と「ボックス」はクルクル回るという状態
。ウマ君が作った「出目金」と「ボックス」はクルクル回るという状態 。「黒ッキー」は、傾きながら泳ぐという、まるで弱ったベイトのようでした
。「黒ッキー」は、傾きながら泳ぐという、まるで弱ったベイトのようでした 。予想外は、「まだらフィッシュ」。リップもありませんが(実質的な失敗作)、一番プリプリとおしりを振りながら泳ぎました
。予想外は、「まだらフィッシュ」。リップもありませんが(実質的な失敗作)、一番プリプリとおしりを振りながら泳ぎました 。
。つまり、リップがついているもので泳いだのは、「レモンクッキー」だけ。もう少し研究しないといけないようです。次への課題です
 。
。次に釣れるかどうか・・・それぞれ数回ずつ投げました。まず一番期待度の高かった「シード」君。全然でした

 。今度はこれに羽根でもつけてみようかと・・・。「あっかんべぇ~」と「レモンクッキー」は泳ぎも静かなら、釣果も静か・・・沈黙でした
。今度はこれに羽根でもつけてみようかと・・・。「あっかんべぇ~」と「レモンクッキー」は泳ぎも静かなら、釣果も静か・・・沈黙でした 。「黒ッキー」と「まだらフィッシュ」は追いかけてくることはありましたが、やはり沈黙
。「黒ッキー」と「まだらフィッシュ」は追いかけてくることはありましたが、やはり沈黙 。普段でもスプーン以外はあまり釣れないので、致し方ありません。・・・で、最後に「錘スプーン」。釣れました。3投で3尾
。普段でもスプーン以外はあまり釣れないので、致し方ありません。・・・で、最後に「錘スプーン」。釣れました。3投で3尾 。これは爆釣スプーンかぁぁあああ
。これは爆釣スプーンかぁぁあああ って思って、4投目。
って思って、4投目。「プチッ
 」
」・・・・・・・・・・
 。林の奥へ飛んで逝ってしまいました
。林の奥へ飛んで逝ってしまいました 。
。家に帰り、早速大量生産しました
 。今回は色をつけたり、ウレタンコートまでしちゃいました。2個だけ無加工にしてあります。ついでに木粉ねんどを使って、棒のやつもつくってみました。
。今回は色をつけたり、ウレタンコートまでしちゃいました。2個だけ無加工にしてあります。ついでに木粉ねんどを使って、棒のやつもつくってみました。
さて、これはどうでしょうか・・・
 。
。ルアー作り初心者は、こういった簡単なものから始めるのがよさそうです

 。
。 2011年02月02日
新たな仲間
2月2日(水)
先日作ったルアーに新たな仲間が増えました。なぜか数式が書いてあるものもあります 。こんなにいっぱいになりました
。こんなにいっぱいになりました 。
。

使えそうなもの、使えそうにないもの・・・いろいろです
 。
。
ところで、一日早いですが、鬼が来ました。

・・・が、豆を投げつけられ、退散しました 。
。
先日作ったルアーに新たな仲間が増えました。なぜか数式が書いてあるものもあります
 。こんなにいっぱいになりました
。こんなにいっぱいになりました 。
。
使えそうなもの、使えそうにないもの・・・いろいろです

 。
。ところで、一日早いですが、鬼が来ました。

・・・が、豆を投げつけられ、退散しました
 。
。2011年01月31日
手術
1月31日(月)
昨夜のお風呂でのスイムテストの結果ですが、ほとんどのものはとりあえず正しい向きで泳ぎましたが、1尾だけお尻が浮いてまともに泳ぎませんでした。ウマ君の「ボックス」です 。
。
おそらくこの個体は錘が前寄りにある上に、臀部が太いので浮力があり、その結果お尻が浮いてしまったようです。
よって手術を施行することになりました 。
。
まず、底部分に丸い穴をあけて、ジェル状の瞬間接着剤をたっぷり入れて、ガンダマを埋め込み、その上からウレタン塗装をしました 。
。

水の中に入れてみましたが、もうお尻は浮きません。とりあえず手術成功です
 。
。
ついでに中通し錘(0.5号)からスプーンを作ってみました。少しけずったので、おそらく1.5gくらいです。これは叩いて穴をあけただけなので、超簡単

でも鉛は柔らかすぎるし、環境にも良くないかも・・・他の素材を探してみます 。ネットで見てると、空き缶や画鋲でスプーン作っている人がいるみたいです
。ネットで見てると、空き缶や画鋲でスプーン作っている人がいるみたいです 。
。
そして、すでに次のルアー(ミノーの予定)と予備のシード君の仕込みをしました。

1個だけわたし、残りはウマ君が色を塗る予定なんです 。
。
昨夜のお風呂でのスイムテストの結果ですが、ほとんどのものはとりあえず正しい向きで泳ぎましたが、1尾だけお尻が浮いてまともに泳ぎませんでした。ウマ君の「ボックス」です
 。
。おそらくこの個体は錘が前寄りにある上に、臀部が太いので浮力があり、その結果お尻が浮いてしまったようです。
よって手術を施行することになりました
 。
。まず、底部分に丸い穴をあけて、ジェル状の瞬間接着剤をたっぷり入れて、ガンダマを埋め込み、その上からウレタン塗装をしました
 。
。
水の中に入れてみましたが、もうお尻は浮きません。とりあえず手術成功です

 。
。ついでに中通し錘(0.5号)からスプーンを作ってみました。少しけずったので、おそらく1.5gくらいです。これは叩いて穴をあけただけなので、超簡単


でも鉛は柔らかすぎるし、環境にも良くないかも・・・他の素材を探してみます
 。ネットで見てると、空き缶や画鋲でスプーン作っている人がいるみたいです
。ネットで見てると、空き缶や画鋲でスプーン作っている人がいるみたいです 。
。そして、すでに次のルアー(ミノーの予定)と予備のシード君の仕込みをしました。

1個だけわたし、残りはウマ君が色を塗る予定なんです
 。
。 2011年01月30日
工作
1月30日(日)
今週末ももちろん海で粉を撒いてきました。そして、エサは2度ほどかじられました
 (・・・って喜んでる場合か
(・・・って喜んでる場合か )。フカセではボウズが続いておりますが、水温7度で釣ってる方がおかしい
)。フカセではボウズが続いておりますが、水温7度で釣ってる方がおかしい
 。・・・ということにしておいてください
。・・・ということにしておいてください 。
。
今週末はウマ君に別用があったので、ウマ君との管釣りトラウトはなしでした
 。
。
・・・ということでは、今週末は釣りでは記事にならないので、本日は親子の工作をご紹介します。
ジャジャーン

最近トラウトにはまっている親子は、ルアーを自分たちで作ってみようということになりました
 。材料はこちら
。材料はこちら 。
。

ダイソーの木粉ねんどとあとはステンレス棒、目玉、リップボード、ウレタンコート、それ以外に釣り用のガンダマと糸オモリ、100円ショップの瞬間接着剤とエポキシ接着剤、絵具にマジックペン、ヤスリとハサミを用意しました 。
。
まずはステンレス棒を適当に切って曲げて、糸オモリを巻いて、ガンダマをつけて、1.5~2グラムくらいになるように調整。

そして、木粉ねんどでこれまた適当に形を作り、自分のものはそれっぽく 、ウマ君が作ったやつは左右上下のバランスをよくする最低限の調整を加えます
、ウマ君が作ったやつは左右上下のバランスをよくする最低限の調整を加えます 。
。

1日乾燥させると固まるので、アイとボディーの隙間に瞬間接着剤を流し入れ、乾いたら全体にヤスリをかけて形を整え、水彩絵の具やマジックペンを使って色を塗って再び乾かします。

次にリップをハサミで切り出します。その後、ヤスリで角を落とします。

そしてリップを差し込みたいところにカッターで切り目を入れて、やはり瞬間接着剤で固定。目玉も瞬間接着剤でつけます。乾いた後、仕上げにエポキシ系接着剤(2種類まぜるやつ)を全体に塗るとできあがりです 。本当はウレタンコートをするつもりでしたが、乾燥に時間がかかるのと重ね塗りをしないといけないので、今回は面倒なので、ウレタンコートの代わりにエポキシ系接着剤を全体に塗りました(ロッドのガイド修理に使ったやつです)。
。本当はウレタンコートをするつもりでしたが、乾燥に時間がかかるのと重ね塗りをしないといけないので、今回は面倒なので、ウレタンコートの代わりにエポキシ系接着剤を全体に塗りました(ロッドのガイド修理に使ったやつです)。
そして最後にふたりで名前を付けました。わたしのが赤い字 、ウマ君のが青い字
、ウマ君のが青い字 です。
です。

初めて作った割には、なんとなくそれっぽくなりました。今晩、お風呂でスイムテストをする予定です 。たぶん半分くらいは泳がないかもしれませんが・・・
。たぶん半分くらいは泳がないかもしれませんが・・・ 。来週末くらいには、実戦に投入し、結果をお知らせします。できれば、1尾くらいは釣ってみたいです
。来週末くらいには、実戦に投入し、結果をお知らせします。できれば、1尾くらいは釣ってみたいです 。
。
乾燥を待つ時間が面倒なんですが、結構楽しいので、釣れたら、また作ってしまいそうです 。
。
今週末ももちろん海で粉を撒いてきました。そして、エサは2度ほどかじられました

 (・・・って喜んでる場合か
(・・・って喜んでる場合か )。フカセではボウズが続いておりますが、水温7度で釣ってる方がおかしい
)。フカセではボウズが続いておりますが、水温7度で釣ってる方がおかしい
 。・・・ということにしておいてください
。・・・ということにしておいてください 。
。今週末はウマ君に別用があったので、ウマ君との管釣りトラウトはなしでした

 。
。・・・ということでは、今週末は釣りでは記事にならないので、本日は親子の工作をご紹介します。
ジャジャーン


最近トラウトにはまっている親子は、ルアーを自分たちで作ってみようということになりました

 。材料はこちら
。材料はこちら 。
。
ダイソーの木粉ねんどとあとはステンレス棒、目玉、リップボード、ウレタンコート、それ以外に釣り用のガンダマと糸オモリ、100円ショップの瞬間接着剤とエポキシ接着剤、絵具にマジックペン、ヤスリとハサミを用意しました
 。
。まずはステンレス棒を適当に切って曲げて、糸オモリを巻いて、ガンダマをつけて、1.5~2グラムくらいになるように調整。

そして、木粉ねんどでこれまた適当に形を作り、自分のものはそれっぽく
 、ウマ君が作ったやつは左右上下のバランスをよくする最低限の調整を加えます
、ウマ君が作ったやつは左右上下のバランスをよくする最低限の調整を加えます 。
。
1日乾燥させると固まるので、アイとボディーの隙間に瞬間接着剤を流し入れ、乾いたら全体にヤスリをかけて形を整え、水彩絵の具やマジックペンを使って色を塗って再び乾かします。

次にリップをハサミで切り出します。その後、ヤスリで角を落とします。

そしてリップを差し込みたいところにカッターで切り目を入れて、やはり瞬間接着剤で固定。目玉も瞬間接着剤でつけます。乾いた後、仕上げにエポキシ系接着剤(2種類まぜるやつ)を全体に塗るとできあがりです
 。本当はウレタンコートをするつもりでしたが、乾燥に時間がかかるのと重ね塗りをしないといけないので、今回は面倒なので、ウレタンコートの代わりにエポキシ系接着剤を全体に塗りました(ロッドのガイド修理に使ったやつです)。
。本当はウレタンコートをするつもりでしたが、乾燥に時間がかかるのと重ね塗りをしないといけないので、今回は面倒なので、ウレタンコートの代わりにエポキシ系接着剤を全体に塗りました(ロッドのガイド修理に使ったやつです)。そして最後にふたりで名前を付けました。わたしのが赤い字
 、ウマ君のが青い字
、ウマ君のが青い字 です。
です。
初めて作った割には、なんとなくそれっぽくなりました。今晩、お風呂でスイムテストをする予定です
 。たぶん半分くらいは泳がないかもしれませんが・・・
。たぶん半分くらいは泳がないかもしれませんが・・・ 。来週末くらいには、実戦に投入し、結果をお知らせします。できれば、1尾くらいは釣ってみたいです
。来週末くらいには、実戦に投入し、結果をお知らせします。できれば、1尾くらいは釣ってみたいです 。
。乾燥を待つ時間が面倒なんですが、結構楽しいので、釣れたら、また作ってしまいそうです
 。
。 














